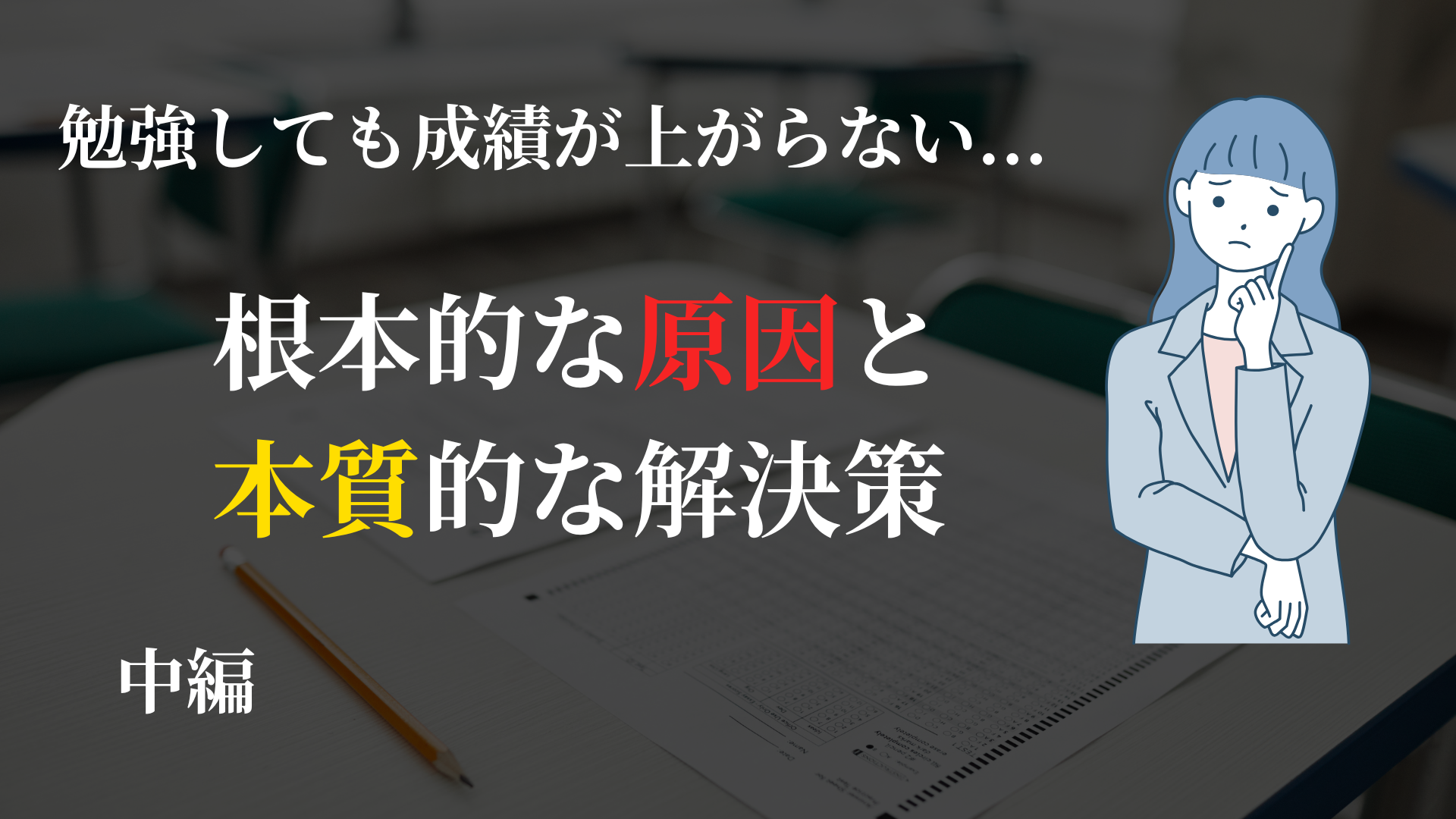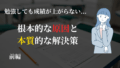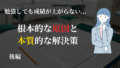今回は、前回に引き続き勉強しているのに成績が上がらない/伸び悩んでいる中高生に向けて、その原因と本質的な解決策を書きます。
・毎日何時間も勉強しているのに、成績が上がらない/伸び悩んでいる
・なぜ、成績が上がらないのか原因がわからない
・表面的な解決法ではなく、本質的な解決策を知りたい
今回の内容は、一般的に塾が言わない(意図的に言わない)内容になります。
結論
最初に結論を書きます。
勉強しても成績が上がらない原因は、
①マインド(スタンス・姿勢)レベルが低い
②基礎固めの基準設定が曖昧
③目的と手段が混同している
④言語化レベル・読解力レベルが著しく低い
⑤勉強の作業化
⑥表面的な勉強法で勉強している
⑦インプット・準備不足
⑧生活習慣の乱れ
この8つが根本的な原因です。
控えめに言いますが、上記8つが改善されない限り、現状は改善しにくいでしょう。
この記事では残りの④~⑥の内容を扱います。①~③に関しては、前回の記事を参照ください。
言語化レベル・読解力レベルが著しく低い
言語化レベル・読解力レベルが低いと高校受験・大学受験の話になりません。
言語化レベル
言語化レベル=言語化能力と呼ばれるものになります。
仕事柄、中高生と話したとき、
・主語または述語がない
・そもそも言葉が出てこない
・質問と答えがかみ合っていない
など。上記のような状態の人は、ほぼ成績が横ばいもしくは下降状態です。
また、街で話している高校生の会話で「やばい」「それな」「くさ(草)」このあたりの言葉を使っている人も見かけます。
これで会話が成立していることに驚きです。
たかが言語化と思うかもしれませんが、偏差値が高い人や成績が向上傾向にある人の言葉の使い方は適切です。
これからの時代、言語化能力がより求められます。
言語化に関する詳細はこちらの記事で。
言語化能力を高める行動に関してはこちらの記事で。
読解力レベル
読解力は文章から情報を正確に読み取る力です。
読解力が大事な理由は分かりますよね?
正確に文章を読めとることができないと、何が問われているのかを見失います。
これは現代文に限らず、英語や数学も同様です。
私の主観的な考えですが、現代文も数学も本質の考え方や解き方は同じだと考えています。
(あと、英語の長文読解も)
使われている表記(言語)が
・現代文→日本語
・数学→数字、文字式
・英語の長文読解→英語
というだけです。
「読解力を上げるにはどうしたらいいですか?」とよく質問を受けます。
シンプルに活字に慣れてください。
・本や新聞を読む
・ニュース記事を読む
・自分のためになるブログ記事を読む
そうすれば、自然に読解力は身に付きます。
勉強の作業化
90%の中高生の勉強は作業化している
勉強の作業化と聞くと、
・授業の板書をただ写すこと
・授業動画を意味もなく聞いていること
・問題の解答をそのまま写すこと
このあたりを思うかもしれない。
確かに、上記も当てはまるが、多くの中高生は
問題を解くことや講義系参考書を読むこと、定期的な授業や面談(進捗状況を確認したりするもの)ですら作業化しています。
生徒本人は、真剣に取り組んでいるかもしれませんが、作業化しています。
残酷なことに、塾や予備校の先生はそれを指摘してくれないことが多いです。
英語の単語帳を何度も繰り返しているのに覚えられない人は、単語帳を勉強すること自体がメインになっています。単語帳をやるという作業です。
作業化した勉強は時間のムダです。
作業化してしまう原因は、意図がないことです。
勉強を「なんとなく」でやってしまいます。勉強しているのに思考停止状態です。
よく「今日は10時間以上勉強した!」と勉強時間に満足している受験生がいますが、中身が伴っていないことが多いです。
「なぜ?」を考える
成績が伸びる生徒の勉強には、必ず「なぜ?」という問いかけがあります。
「なぜこの公式を使うんだろう?」
「なぜこの品詞の働きが名詞修飾なんだろう?」
「なぜこの歴史的出来事が起きたんだろう?」
このように、「なぜ?」を追求するプロセスこそが、知識をバラバラの「点」から、繋がりを持った「線」に変え、応用力を生み出すトリガーになります。
「作業化」された勉強では、この「なぜ?」が抜け落ちてしまいます。
結果、いくら問題集を解いても、覚えた知識は断片的で、少しひねられた問題が出たり、異なる角度から問われたりすると、途端に手も足も出なくなってしまいます。
教科書を読んでも、問題集の解説を読んでも、「わかったつもり」のまま次に進んでしまうのは非常に危険です。
「わかったつもり」は、脳が「これ以上考えるのは面倒だな」とサボっている状態です。
本当に理解できているかどうか
・その内容を、誰かに自分の言葉で説明できるか
・類題が出た時に、初見で解けるか
上記2つで確認してみてください。
勉強は新しい知識を習得し、使えるようにするものです。
作業化しないでください。
表面的な勉強法で勉強している
「表面的な勉強法?」と思った方へ
まずは下の一例を読んでください。
==============================
【シチュエーション】
あなたは腹痛がひどく病院に行きました。
あなた:「昨日の夜から腹痛なんです」
医者:「最近、腹痛の患者さんが多いですからね。この薬A、B、Cは有名な医者が良いと言っているので、Aから試してみましょう。」
==============================
あなたの腹痛の原因が食べすぎかもしれないし、あるいは何かウイルスによる病気かもしれません。
しかし、医者は有名な医者が良いといっているからという理由で、薬を提案・処方しています。
これと同じことが受験勉強あるいは塾・予備校業界で起きています。
勉強法ビジネスの流行
大学受験(高校受験)に対し、多くの受験生が「表面的な勉強法」に飛びついてしまいます。
根底には、勉強法ビジネスが存在しています。
書店に行くと分かりますが、大学受験の参考書コーナーの近くに勉強法に関する書籍があふれています。これまで十冊以上読みましたが、9割は同じような内容でした。
Youtubeも同様です。同じようなことを言っています。
(ちなみに、1割の本はマインドや認知心理学のことが書かれていました。)
ただ受験生から目線で考えると、魅力的に見えるものばかりです。が、、、
書店に並んでいる勉強法に関する書籍の9割が専門家ではないに1人の成功者の意見だととらえてください。このブログもそうですが…(笑)
また、SNSで良く見られる「裏技」や「ズルい勉強法」なども表面的な勉強法です。
いわゆるテクニックです。
テクニックをいくら習得しても基礎がボロボロだと入試問題には歯が立ちません。
例えるなら、清潔感のない男がカッコいいセリフで女性を口説いているような状態です…
(女性なら理解できると思います)
テクニックや聞こえのいい表面的な勉強法の裏には、勉強法ビジネスの存在によってできた都合のいい勉強法だということを頭の片隅に置いといてください。
勉強法=HOW
ここで私が伝えたいことは勉強法=HOWということです。
大事なので、もう一度。
勉強法はHOWです。
ビジネスの世界には、ゴールデンサークル理論という考え方があります。
この理論で伝えたいことは、howよりもwhyの方が大事ということです。
why(なぜやるか)の方に趣を置いてください。
本当に役立つ勉強法とは?
先ほど、「1割の本はマインドや認知心理学のことが書かれていました。」とお伝えしました。
本当に役立つ勉強法とは、個別化された勉強法です。
個別化された勉強法とは、「生徒の状況に随時合わせた勉強法」です。
志望校、現状の学力レベル、得意科目、苦手科目、好きな/嫌いな科目、生活習慣、思考特性(性格)、生活環境などを考慮する必要があります。
生活習慣、思考特性、生活環境は無視されがちですが重要です。
生活習慣に関しては、⑧で書きます。
実は、思考特性によって合う/合わない勉強法が決まります。
さらには、向いている学問領域(学科)や職種・業種まで決まります。
これは人相学という学問を勉強すると理解できます。
中高生の皆さんは現状の勉強に余裕があれば、調べてみてください。
話がやや脱線しましたが、ここで伝えたいことは、勉強方法はHOWであり、whyと個人によって変わるということ。
個人の状況に合わせた勉強法が必要ということです。
数値を追う勉強法
8月(2025年)開講予定のMIKOT塾では、「ムリ・ムダ・ムラのない数値を追う個別化勉強法」を軸にしています。
数値で一つ気を付けてほしいポイントがあります。
それは改善すべき数値であるかを判断することです。
最たる例が勉強時間です。
大前提、勉強時間は大事ですが、10時間、16時間勉強したからOKではありません。
「〇曜日は〇時間しかできなかった」
「週に勉強時間が0の日は何日あったか」
などを考えるのは本質ではありません。
内容を理解し、点が取れるかという成果で判断してください。
当たり前のことですが、できない受験生が多いです。
まとめ
今回も前回に引き続き、勉強しているのに成績が上がらない/伸び悩んでいる中高生に向けて、その原因と本質的な解決策を書いてきました。
④言語化レベル・読解力レベルが著しく低い
⑤勉強の作業化
⑥表面的な勉強法で勉強している
上記はあまり塾や予備校の先生が指摘しないことですが、本質をついています。
次回は、残りの⑦と⑧を書きます。
最後まで読むことをおすすめします。
今回は、以上。
最後まで読んでくれてありがとう!