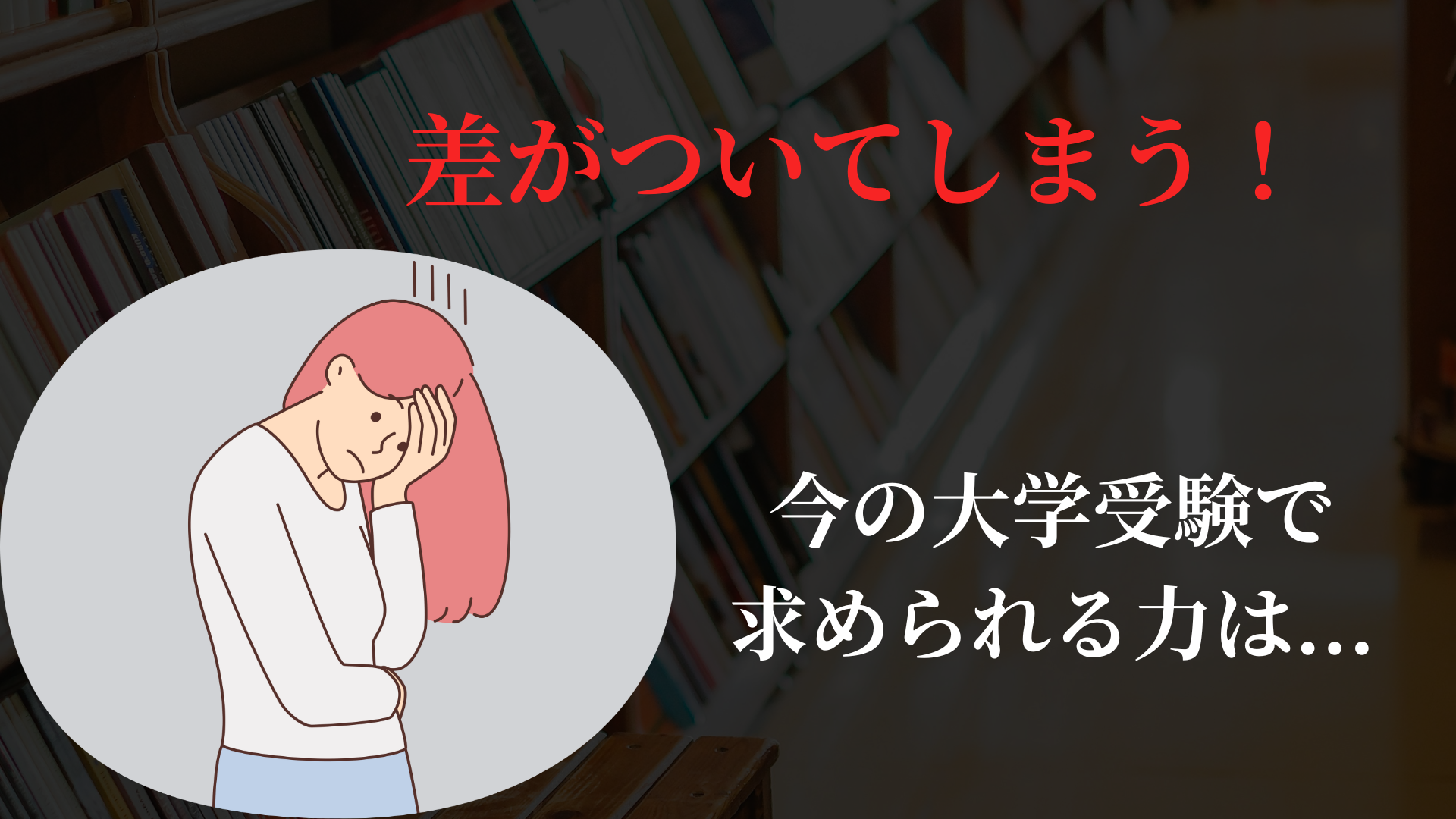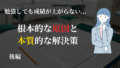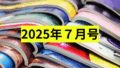今回は、大学入試は読解力と背景知識で差がついてしまうというにわかには信じがたい話を展開していきます。
「設問を読んでもよくわからない」「単語や文法は分かるけど、長文読解になると読めない」といった悩みがある方は該当している可能性が高いです。
この記事では、なぜ、読解力と背景知識で差がついてしまうのか、今日からできる対策を説明します。
「問いが読めない」は読解力
「読解力」と聞くと、多くの人は「現代文の文章を読む力」を思い浮かべるかもしれません。
もちろんそれも含まれますが、ここで言う「読解力」は、もっと広範な意味を持ちます。
それは、「出題者が何を求めているのか」を正確に読み取る力、つまり「設問読解力」のことです。
英語長文
長文の内容はなんとなく理解できた気がするのに、設問の選択肢で迷ってしまい、結局間違った選択肢を選んでしまった。あるいは、本文中の根拠を見つけられずに解答に詰まってしまった。
数学
複雑な問題文を読み解くのに時間がかかりすぎたり、問題の意図を取り違えて、解答の方針が全く見当違いな方向に行ってしまったりした。難しい公式や定理を使おうとして、実はもっとシンプルな解法があったことに気づかなかった。
国語(現代文・古文・漢文)
文章自体は読めたのに、設問が何を問うているのかが曖昧で、解答のポイントがずれてしまった。
「最も適切なものを選べ」という問いなのに、どこも合っているように見えてしまう。
理科・社会
教科書の内容は覚えているはずなのに、グラフや図、史料を用いた問題になると、何が問われているのか分からず、手が出ない。あるいは、記述問題で、覚えた用語をただ羅列してしまい、要求された内容に答えきれていない。
上記は、すべて「読解力」不足が原因で起こります。問題文や設問文で聞かれている問いを読み取ってください。
特に、大学入試は、単純な知識の暗記を問う問題ばかりではありません。
「〇〇の出来事の背景を説明しなさい。」
「筆者の考えと合致するものを、本文中の根拠を挙げながら答えなさい。」
「次のグラフから読み取れる傾向を、2つの観点から述べなさい。」
こうした設問には、「ただ用語を答える」以上の要求が隠されています。
「背景」とは原因のことなのか、それとも時代状況全体のことなのか?
「合致するもの」は複数あるのか?
「2つの観点」とは、それぞれ別の切り口で答えるべきなのか?
これらの問いを正確に読み取れなければ、いくら完璧な知識を持っていても、正解を導き出すことはできません。
読解ができた上で、思考力や判断力、表現力が求められています。
だから読解力が必要です。
背景知識(教養知識)の重要性
多くの受験生が見過ごしているもう一つの重要な要素が背景知識(教養知識)です。
「教養なんて、受験に関係ないでしょ?」「そんなこと勉強してる暇ない!」と思うかもしれません。
教養知識がどのように得点に繋がるのか説明します。
現代文・小論文:読み解くスピードと精度が格段に上がる
現代文や小論文では、普段の生活ではあまり触れることのないような、専門的かつ抽象度の高いテーマの文章が頻繁に出題されます。
例えば、科学技術の倫理、哲学的な思考、社会構造の変化、環境問題、グローバル化、情報化社会、生命倫理、AIやテクノロジー、経済学、言語学など、多岐にわたります。
もし、あなたが「資本主義」や「ポストモダン」といったテーマについて、ある程度の知識を持っていたとしましょう。
文章を読み始めた瞬間に、「ああ、この文章はあのテーマについて語っているんだな」と、文脈を瞬時に把握することができます。 知らない単語が出てきても、前後の文脈から意味を推測しやすくなりますし、筆者の主張もより深く、正確に理解できるようになります。
特に、以下の3点で有利です。
▶読解スピードの向上
背景知識があることで、文章の展開をある程度予測しながら読むことができるため、一字一句を追うのではなく、効率的に要点をつかむことができます。
これにより、速読力が格段に向上します。
▶理解の深さ
知らない単語が出てきても、背景知識があれば、前後の文脈から意味を推測しやすくなります。
また、筆者の主張や論理展開も、より深く、多角的に理解できるようになります。
例えば、筆者が「〇〇主義」について批判的に述べている場合、その「〇〇主義」がどのような思想であるかを知っていれば、筆者の批判の意図や深みがより鮮明に理解できます。
▶小論文における説得力
小論文に至っては、背景知識はまさに必須の武器です。「AIの発展が社会に与える影響について、あなたの意見を述べなさい」という問いに対し、AIの技術的な側面、倫理的な問題点、経済・社会構造への影響などについて何も知らなければ、説得力のある意見を構築することすらできません。
教養知識が豊富であれば、多角的な視点から論じることができ、深みのある、説得力のある小論文を書くことが可能になります。
逆に、背景知識が全くない場合、単語の一つ一つを追うことに精一杯になり、文章全体を俯瞰して読むことができなくなってしまいます。 結果として、設問に答えられなかったり、時間が足りなくなったりします。
小論文に至っては、背景知識は必須です。
ある国公立大学経済学部の推薦入試の小論文で、設問に「エンジェル投資」という言葉が登場しています。
本文中に、エンジェル投資について簡単に解説してありましたが、知っているのと知らないのでは、読解のスピードにも関わります。
このように、背景知識があるなしでは「スタートラインが違う」という状況をつくります。
残酷ですが…
英語長文:文章の予測が可能になり、速読力も向上する
実は英語長文も、教養知識の恩恵を大きく受けられる科目の一つです。
入試の英語長文は、現代文と同様に、多様なテーマから出題されます。科学論文の抜粋、社会学に関する考察、歴史的事件の解説、文化論など、ジャンルは多岐にわたります。
例えば、「遺伝子組み換え食品の是非」についての英語長文を読んでいるとしましょう。
もし、あなたがそのテーマについて日本語で知っている知識(メリット、デメリット、安全性に関する議論、各国の規制状況など)があれば、
「次はきっと、安全性や倫理的な問題について話すだろう」
「導入による農業の変化に言及するかもしれない」
と文章の展開を予測しながら読むことができます。
予測しながら読むことで、単語や文法を一つ一つ完璧に訳さなくても、文章の骨子を素早く理解できるようになり、結果として速読力が格段に向上します。
得られるメリットをまとめると、
▶速読力の向上
予測しながら読むことで、単語や文法を一つ一つ完璧に訳さなくても、文章の骨子や筆者の主張を素早く把握できるようになります。これにより、英語を読むスピードが格段に向上し、時間制限の厳しい入試で大きなアドバンテージとなります。
語彙力の補完
知らない英単語が出てきたとしても、そのテーマに関する背景知識があれば、「この文脈なら、きっとこういう意味だろう」と、意味を類推できる場面が増えます。これにより、辞書を引く手間が省け、読解のリズムを崩さずに進めることができます。
内容理解の深さ
英語で書かれた専門的な内容でも、日本語で既にそのテーマの概略を理解していれば、よりスムーズに、より正確に内容を理解できます。
教養知識がある人とない人とでは、同じ英語長文を読むスピードと、理解の深さが全く違ってきます。
これは、英語の点数だけでなく、他の科目にも影響を及ぼす「総合的な学力」の差として現れます。
背景知識(教養知識)はどう身に付ければいい?
ここまでで背景知識が重要なことは理解できたと思います。
「でも、教養知識ってどうやって身につければいいの?受験勉強で手一杯なのに…」
と思った方、安心してください。特別な、膨大な時間を割く必要はありません。
教養知識は、日々の生活の中にある好奇心を大切にし、少しだけアンテナを張ることから生まれます。
以下に簡単に背景知識がつく習慣を挙げます。
▶新聞やニュースに触れてみる
社会で今何が起きているのか、科学技術はどこまで進んでいるのか、経済の動きはどうなっているのか。関心を持つことが第一歩です。政治経済や現代社会の知識が直接的に増えるだけでなく、現代文や英語長文のテーマを知る良い機会になります。
▶興味のある本や雑誌、新書を読んでみる
自分の好きな分野(歴史、科学、文学、芸術、映画、音楽、社会問題など)に関する本を読んでみましょう。受験のためではなく、純粋な好奇心から選んでみてください。様々な知識が点として蓄積され、やがて線となり、面となって、あなたの教養知識を形作っていきます
▶ドキュメンタリー番組やYouTubeの解説動画を見てみる
活字を読むのが苦手なら、映像から知識を得るのも非常に有効です。
TEDなどのプレゼンテーション動画や、専門家による解説チャンネルなども、興味深いテーマを分かりやすく学べる良いツールです。
年内に、何かやろうか検討中。
▶学校の授業を「受験のため」だけでなく「知的好奇心」で受けてみる
現代社会、倫理、政治経済、世界史、日本史などの科目は、直接的に教養知識を深める絶好の機会です。教科書の太字だけでなく、本文やコラム、先生の話に耳を傾けることで、思わぬ発見があるかもしれません。
▶「なぜ?」を大切にする習慣
最も大切なのは、日常生活や学習の中で出会った事柄に対して、「なぜ?」という問いを投げかける好奇心です。
例えば、
「なぜこのニュースが話題になっているんだろう?」
「なぜこの歴史的出来事が起きたんだろう?」
「この技術は私たちの生活をどう変えるんだろう?」とさらに一歩踏み込んで調べてみることです。
この日々の地道な積み重ねが、やがてあなたの「教養知識」となります。
~宣伝~
8月(2025年)開講予定にMIKOT塾の英語講座では、専門性の高いテーマに関して、
現代文や小論文でも使える背景知識を含めた解説を行う予定です。
まとめ
今回は、読解力と背景知識という一見、受験に関係なさそうなものが大事であるという話を説明してきました。
読解力と教養知識は、単に大学入試のためだけの一時的な力ではなく、大学に入ってからも、そして社会に出てからも、物事を深く理解し、自分の言葉で考え、表現し、問題解決をしていくために不可欠な、まさに一生ものの普遍的な力です。
今からでも遅すぎるということは決してありません。 日々の勉強の中で、「なぜ?」という好奇心を常に持ち続け、文章を正確に読み解く力を意識して磨いていきましょう。
今回は以上。
最後まで読んでくれてありがとう!