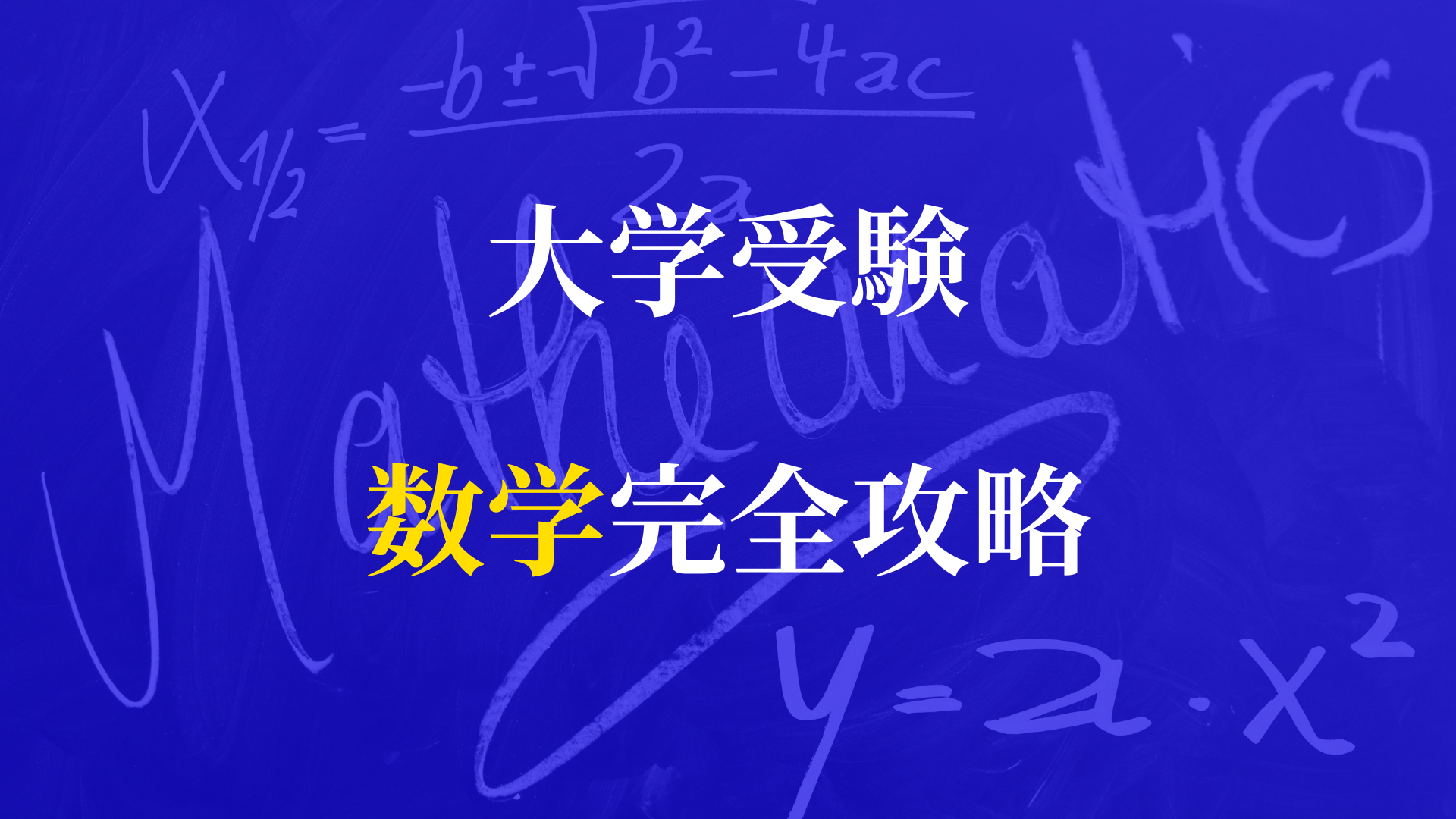今回は、大学受験の数学の攻略法を解説していきます。
この記事を読むべき人
・数学の成績が伸び悩んでいる人
・受験で数学を得意科目にして得点源にしたい人
今回もかなり貴重な内容です。
数学は「ひらめき」じゃない!
最初に断言します。
数学は「ひらめき」ではありません。
「数学はセンスが必要だから、自分には無理だ…」
「公式は覚えているのに、問題になると全然解けない…」
「問題集を何周もしたのに、模試の点数が伸び悩んでいる…」
大学受験の数学に対して、こんな風に漠然とした苦手意識や不安を抱いませんか?
多くの受験生が「数学はひらめきが必要な科目だ」と思い込みがちですが、実はそれは大きな誤解です。
大学入試の数学は「ひらめき」や「才能」だけで解くものではありません。
必要なのは、明確な「概念理解」と「解法の暗記」、そして、それらを使いこなすための論理的な思考プロセスです。
これらを身につけ、演習を重ねれば、誰でも安定して高得点を狙えるようになる科目なのです。
大学受験数学の本質
大学受験数学の本質は何か?
それは、「概念理解」と「解法の暗記」のバランスです。
一見相反するように見える二つの要素のバランスの上に成り立っており、どちらか一方だけでは、高得点は望めません。
概念理解の重要性:なぜそうなるのか?を深く掘り下げる力
「概念理解」とは、単に公式や定理を覚えるだけでなく、
「なぜその公式が成り立つのか」
「その定理が何を意味するのか」
「どのような状況で使えるのか」
といった、その知識の背景にある原理や本質を深く理解する力のことです。
▶応用問題への対応力
入試で出題される問題は、教科書の例題をそのまま出すような単純なものばかりではありません。
特に難関大学では、複数の単元を組み合わせた問題や、初見の状況設定で問われる応用問題が頻出します。 公式を丸暗記しているだけでは、少し形が変わったり、見慣れない設定になったりすると、途端に手も足も出なくなってしまいます。
しかし、その公式や定理が「なぜ成り立つのか」「何を意味するのか」という概念を深く理解していれば、問題の形が変わっても、その本質を見抜き、柔軟に対応することができるようになります。
▶思考の柔軟性
概念を理解している生徒は、一つの問題に対して複数の解法を思いついたり、最適な解法を選択したりする柔軟な思考が可能です。これは、単に答えを出すだけでなく、より効率的で美しい解法を見つける力にも繋がります。
▶忘れにくい知識
丸暗記した知識は忘れやすいものですが、概念を理解し、論理的な繋がりの中で覚えた知識は、脳に深く定着し、忘れにくくなります。
解法の暗記」の重要性:パターンを習得し、効率を高める力
「解法の暗記」とは、典型的な問題パターンや、その問題を解くための標準的なアプローチ(解法の手順)を、体に染み込ませるように習得することです。
▶解答スピードの向上
入試では時間制限があります。初見の問題でも、典型的な解法パターンが頭に入っていれば、一から考え込む時間を短縮し、スムーズに解答プロセスを進めることができます。
これは、限られた時間で高得点を取るために不可欠な要素です。
▶基礎問題の確実な得点
入試問題には、必ず基礎的な問題も含まれています。これらの問題で確実に得点するためには、解法パターンを正確に暗記し、ミスなく解答できる力が求められます
▶応用問題への足がかり
応用問題も、実は複数の基本解法パターンを組み合わせたものであることがほとんどです。
基本的な解法パターンをしっかり暗記していれば、応用問題を見たときに、「これはあの解法とこの解法を組み合わせれば解けるかもしれない」といった発想が生まれやすくなります。
どちらか一方では不十分!「バランス」が合格への鍵
結論として、大学受験数学では「概念理解」と「解法の暗記」のどちらか一方だけでは不十分です。
概念理解だけでは…
問題を解くスピードが遅くなったり、典型問題でも「一から考える」癖がついてしまい、時間切れになる可能性があります。
解法の暗記だけでは…
少しでも問題の形が変わると対応できなくなり、応用問題で全く歯が立たなくなります。
理想的なのは、「概念を深く理解した上で、その概念を適用する典型的な解法パターンを効率的に暗記し、使いこなせるようになる」ことです。この二つをバランスよく学習し、相互に作用させることで、数学の総合力が飛躍的に向上します。
数学学習の二つの領域:インプットとアウトプット
数学の学習プロセスは、大きく「インプット」と「アウトプット」の二つの領域に分けられます。この二つの領域を意識し、効果的に循環させることが、成績向上の鍵となります。
インプット領域:知識を「取り込む」フェーズ
インプット領域とは、新しい知識や概念、解法パターンを頭の中に「取り込む」フェーズです。
【やること】
▶教科書や参考書の読み込み
新しい単元の概念や定理、公式を理解する。
▶授業の受講
先生の解説を聞いて、新しい知識を学ぶ。
▶公式や定理の導出過程の理解
「なぜそうなるのか」を深く掘り下げる。
▶基本例題の解法を理解する
解答を読み、解法の流れやポイントを把握する。
【インプットの質を高めるポイント】
▶「わかったつもり」をなくす
ただ目で追うだけでなく、「なぜ?」を常に自問自答し、納得できるまで深く理解することを心がけましょう。
▶「自分の言葉で説明できるか」を基準に
概念や公式の導出過程を、誰かに教えるつもりで説明できるかどうかが、真の理解の証です。
▶「なぜこの解法なのか」を理解する
解答をただ覚えるだけでなく、その解法が選ばれる理由、他の解法との比較などを考えることで、解法の本質を理解できます。
アウトプット領域:知識を「使う」フェーズ
アウトプット領域とは、インプットした知識を実際に「使う」ことで、定着させ、応用力を高めるフェーズです。
【やること】
▶問題演習
実際に問題を解き、解法を適用する。
▶解答の記述
自分の思考プロセスを論理的に記述する。
▶間違えた問題の分析
なぜ間違えたのか、どこでつまずいたのかを特定する。
▶解説の読み込みと再考
自分の解答と模範解答を比較し、より良い解法や考え方を見つける。
▶人に説明する
自分が理解した内容を、他の人に説明してみる。
【アウトプットの質を高めるポイント】
▶「解きっぱなし」にしない
問題を解いて、丸つけをして終わり、では学習効果は半減します。間違えた問題は必ず分析し、復習しましょう。
▶「なぜ間違えたのか」を深掘り
ケアレスミスなのか、知識不足なのか、概念理解が曖昧なのか、思考プロセスが間違っていたのか、原因を特定することが重要です。
▶「別解」を検討する
一つの問題に対して、複数の解法がないか考えてみましょう。
これにより、思考の柔軟性が養われます。
▶時間制限を設ける
入試本番を意識し、制限時間内に問題を解く練習をすることで、解答スピードとプレッシャーへの対応力を高めます。
大学受験数学の具体的な勉強法

ここでは、上記の「概念理解」「解法の暗記」「インプット」「アウトプット」を意識した、具体的な数学の勉強法をステップバイステップで解説します。
ステップ1:徹底的な概念理解(インプットの質を高める)
このステップでは、新しい単元を学ぶ際に、その「核」となる概念を深く理解することに注力します。
▶教科書・講義系参考書を読み込む
ただ読むだけでなく、「なぜそうなるのか?」という問いを常に持ちながら読み進めてください。
公式や定理が出てきたら、その導出過程を必ず自分の手で書き出してみてください。(得に数Ⅲ)
丸暗記ではなく、背景を理解することで、忘れにくく、応用が利く知識になります。
分からない箇所があれば、すぐに先に進まず、図を描いたり、具体例を考えたりして、納得できるまで考え抜きましょう。それでも分からなければ、先生や友達に質問してください。
▶例題の解説を熟読する
教科書や参考書に載っている例題は、その単元の基本的な概念がどのように問題に応用されるかを示す「典型」です。
解答を隠して、まず自分で解法の方針を立てます。
その上で、解説を熟読し、自分の考え方と模範解答の考え方を比較します。
「なぜこの解法を選ぶのか」「このステップは何のためにあるのか」といった、解法の意味を理解することが重要です。
ステップ2:基本問題による解法のインプット(理解を伴う暗記)
概念理解が進んだら、次はそれを具体的な問題に適用する「解法」を体に染み込ませる段階です。
▶基本問題集を徹底的に繰り返す
教科書傍用問題集の基本例題・演習問題レベルを徹底的に繰り返しましょう。
「解法を覚える」ことを意識して取り組みます。最初は「解法を真似る」ことから始めてください。
例題の解答を参考にしながらでも構いません。
目標は「何も見ずにスラスラ解ける」状態です。
▶「理解を伴う暗記」を心がける
ただ解答を丸暗記するのではなく、「なぜこの解法が使えるのか」という概念理解と結びつけて暗記するようにしてください。
例えば、二次関数の最大・最小問題なら、「平方完成して軸と定義域の位置関係で場合分けする」という解法パターンを暗記しつつ、「なぜ軸の位置で場合分けが必要なのか」という概念を理解しておく、といった具合です。
▶反復練習の重要性
一度解けた問題でも、間隔を空けて繰り返し解くことで、解法が長期記憶に定着します。
「忘却曲線」を意識し、忘れる前に復習するサイクルを作りましょう。
ステップ3:演習によるアウトプットと弱点発見
基本問題の解法が身についたら、実際に問題を解くことでアウトプットし、自分の弱点を発見する段階です。
そこで、注意点を解説します。
▶「解きっぱなし」にしない
問題を解いて、丸つけをして終わり、では学習効果は半減します。
間違えた問題は必ず分析する習慣をつけましょう。
ケアレスミスなのか?
計算ミス、写し間違いなど。→ 集中力、見直しの習慣を改善。
知識不足なのか?
公式や定理を覚えていない。→ ステップ1に戻り、概念理解と暗記を徹底。
概念理解が曖昧なのか?
公式は知っているが、使いどころが分からない。→ ステップ1に戻り、深く掘り下げる。
思考プロセスが間違っていたのか?
解法の方針が立てられない、途中で行き詰まる。→ ステップ2に戻り、類似問題の解法を再確認。
▶解説を徹底的に読み込む
自分の解答と模範解答を比較し、より効率的で美しい解法(シンプルな解法というイメージです)や、自分が気づかなかった考え方を見つけましょう。
▶「別解」を検討する
一つの問題に対して、複数の解法がないか考えてみましょう。
これにより、思考の柔軟性が養われます。
▶「解き直しノート」を作る
間違えた問題や、解法に迷った問題は、問題と模範解答、そして「なぜ間違えたのか」「どう考えればよかったのか」という反省点をまとめておきましょう。
これは、自分だけの最強の弱点克服ノートになります。
時間が無い場合はカットしても構いません。
ステップ4:応用問題への挑戦と思考力強化
基礎が固まり、典型問題が解けるようになったら、いよいよ応用問題に挑戦し、思考力をさらに高める段階です。
▶初見問題へのアプローチ
すぐに答えを見ない:
応用問題は、すぐに解けなくても当たり前です。最低でも15分〜30分は、自分で考え抜く時間を持ちましょう。
既知の知識に分解する:
複雑な問題も、実は複数の基本問題の組み合わせであることがほとんどです。問題文を細かく分解し、「この部分はあの単元の知識が使えそう」「この条件はあの公式に繋がるかもしれない」と、既知の知識に落とし込んで考える練習をしましょう。
多角的な視点を持つ:
問題を見たときに、代数的なアプローチだけでなく、幾何的なアプローチ(図を描く)、グラフを用いるアプローチなど、複数の視点から考えてみましょう。
関数の問題では、図を書くことを強くおすすめします。
▶思考のプロセスを重視する
応用問題では、答えを出すことよりも、「どのように考えてその答えにたどり着いたか」という思考のプロセスが重要です。解答を導き出すまでの過程を、論理的に説明できるように練習してください。
これは、記述問題対策にも直結します。
ステップ5:過去問演習と最終調整
入試本番が近づいてきたら、志望校の過去問演習を通して、最終的な実力アップと調整を行います。
- 志望校の傾向分析
- 過去問を解く前に、まずは過去3〜5年分の過去問をざっと眺め、出題形式、頻出単元、問題の難易度、時間配分などを分析しましょう。
- 自分の得意・苦手分野と照らし合わせ、最後の追い込みで何を重点的にやるべきかを見極めます。
- 時間配分の練習
- 本番と同じ時間制限を設けて、過去問を解きましょう。
- どの問題にどれくらいの時間をかけるべきか、難しい問題はどこで切り上げるか、といった時間配分の感覚を掴みます。
- 見直しの時間も考慮に入れて練習しましょう。
- 本番を意識した演習
- 本番と同じ環境(静かな場所、机の上を整理するなど)で、集中して取り組むことで、本番の緊張感に慣れる練習にもなります。
- 解き終わった後は、必ず徹底的に分析し、自分の弱点や課題を洗い出し、最後の最後まで改善を続けましょう。
数学学習を効率化するTIPS
上記のステップを実践する上で、さらに効率を上げるためのヒントです。
問題集は「一冊を完璧に」
あれこれ手を出さず、自分に合った問題集を1冊選び、「完璧に」なるまで繰り返しましょう。
「完璧」とは、その問題集の全ての例題・問題について、「何も見ずに、なぜその解法になるのかを説明しながら、スラスラと解ける」状態を指します。
このレベルまで到達すれば、その単元の基礎は盤石です。
「なぜ」を常に問い続ける
新しい概念や公式、解法に出会ったら、必ず「なぜ?」と問いかけましょう。
- 「なぜこの公式が成り立つんだろう?」
- 「なぜこの解法が有効なんだろう?」
- 「なぜこの条件が与えられているんだろう?」 この問いかけが、あなたの思考力を鍛え、表面的な暗記に終わらない深い理解へと導きます。
解答を「人に説明できる」レベルにする
自分が理解した内容や、問題を解いた解法を、誰かに教えるつもりで説明してみましょう。
- 家族や友達に説明してみる。
- あるいは、誰もいなくても、壁に向かって声に出して説明してみる。 このアウトプットのプロセスを通して、自分の理解が曖昧な点が明確になり、知識がより強固に定着します。
計算練習の重要性
数学は、どんなに思考力があっても、計算ミスをしてしまえば点数になりません。
- 毎日短時間でも計算練習をする習慣をつけましょう。
- 計算ドリルや、問題集の計算部分だけを抜き出して解くなど、工夫してみてください。
- 正確さとスピードの両方を意識して練習することが大切です。
苦手分野の克服法:逃げずに「戻る」勇気を持つ
苦手分野は、多くの生徒が避けて通ろうとしますが、それではいつまで経っても克服できません。
- 「なぜ苦手なのか」を分析する: 概念が理解できていないのか、基本問題の演習量が足りないのか、特定の解法が苦手なのか。原因を特定しましょう。
- 「戻る」勇気を持つ: 苦手分野の根本原因が、さらに前の単元にあることも珍しくありません。
必要であれば、前の学年の内容や、もっと基礎的な参考書に戻って復習する勇気を持ちましょう。 - 集中して取り組む: 苦手分野は、得意分野よりも多くの時間と集中力を要します。計画的に時間を確保し、集中的に取り組むことで、着実に克服できます。
学習記録をつける
毎日の学習時間、解いた問題数、正解数、間違えた問題の分析などを記録しましょう。
- モチベーション維持: 自分の努力が可視化され、成長を実感できます。
- 学習の振り返り: どこでつまずいているのか、どの分野の学習が不足しているのかなど、客観的に自分の学習状況を把握できます。
まとめ
大学入試の数学は、決して「ひらめき」や「才能」だけで決まる科目ではありません。
「概念を深く理解し、解法を効率的に暗記し、それを問題に応用する」という、地道で論理的なプロセスを積み重ねることで、誰でも着実に力を伸ばすことができます。
「なぜ?」という問いを大切にし、インプットとアウトプットの循環を意識した学習を継続すれば、必ず数学はあなたの「得意科目」となり、志望校合格への強力な武器となるはずです。
最後まで諦めず地道に取り組んでください。
今回は、以上。
最後まで読んでくれてありがとう!
お知らせ!
8月(2025年)開講予定のMIKOT塾の詳細はこちら。