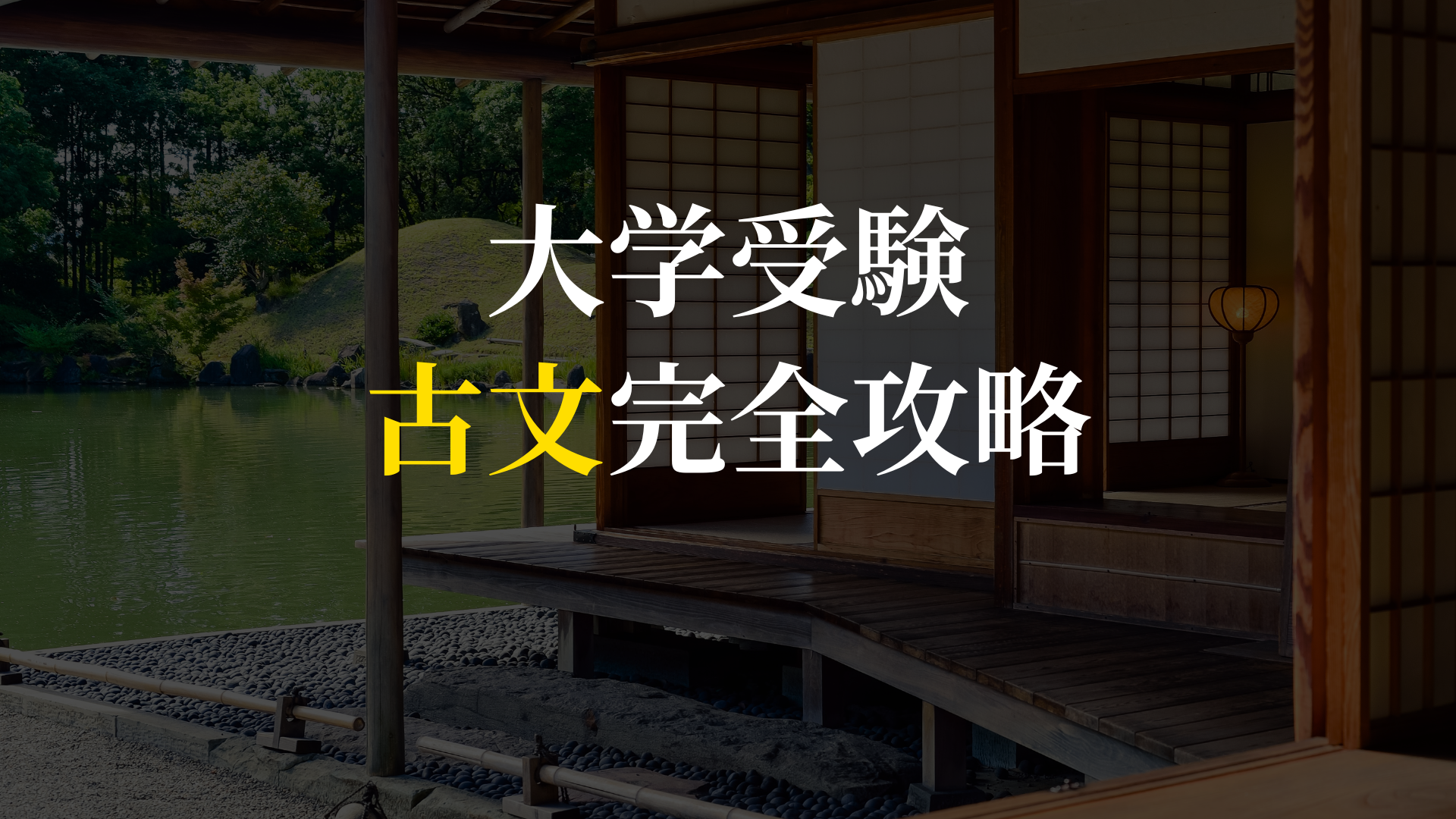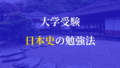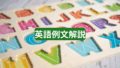今回は、大学受験における古文の解き方や日常の勉強法を具体的に解説していきます。
こんな人におすすめ
・古文は単語や文法を覚えているのに、なぜか点数が取れない
・文章の意味が全くつかめない
・どうやって勉強していいか分からない
多くの人が単語や文法を「暗記科目」と捉えがちですが、入試で安定して得点するには、それらを
「道具」として使いこなし、文章を論理的に読み解く力が不可欠です。
今回の記事では、単なる知識の暗記に終わらない、実践的で具体的な読解戦略と解答プロセスを徹底解説します。入試で問われる古文の本質から、問題形式別の具体的なアプローチ、そして今すぐ実践できる勉強法まで解説していきます。
大学受験の古文
古文は「言語」としてとらえることが重要です。
現代文と同様、古文もまた「客観性」が問われる科目です。
しかし、古文にはそれに加えて、現代とは異なる「言語」としての本質を理解する必要があります。
感想文ではない!筆者や登場人物の心情を論理で読み取る科目
古文を読んで「風流だなぁ」「かわいそうだなぁ」と感傷に浸るだけでは、入試問題は解けません。
(趣味で読むのはいいですが…)
古文で問われるのは、「なぜこの登場人物はこのような行動をとったのか」「この文から読み取れる心情は何か」といった、文章の表面に書かれていない背景や心の内を、本文の記述から論理的に推測する力です。
客観的な根拠とは、本文中の特定の語句(例:「〜ば」などの接続助詞)や、古文常識、対比関係、因果関係などです。
これらの根拠を基に、作者や登場人物の感情や行動を推論する力が、古文の得点を左右します。
思考力を問うツールとしての古文
現代文と同様、古文もまた、単なる暗記力ではなく、以下の「思考力」を測るツールです。
要約力
→物語の複雑な展開から要点を抜き出し、簡潔にまとめる力。
分析力
→誰が誰に話しかけているのか(主語の特定)、登場人物の相関関係、対比関係などを見抜く力。
推論力
→古文常識や文脈から、省略された主語や目的語、さらには心情を論理的に推測する力。
表現力
→読み取った内容を現代語で正確かつ簡潔に表現する記述力
古文でこれらの力を試されているのは意外かもしれません。
古文読解の全体像:問題を解くための3つのステップ

古文の問題に取り組む際も、現代文と同じく、以下の3つのステップを意識することが重要です。
ステップ1:設問を先に読む(ゴール設定)
長文を読み始める前に、必ず設問に目を通しましょう。
特に古文では、このステップが重要です。
▶目的意識を持つ
誰が何について問われているのか、傍線部が指す内容は何かを把握することで、本文を読みながら
「主語」や「心情」に意識を集中できます。
▶キーワードの把握
設問中に含まれるキーワードや、本文中の特定箇所を指す傍線部を事前に確認することで、本文読解時にその箇所に意識を集中できます。
▶問題形式の確認
選択式なのか、記述式なのか、敬意の対象を問う問題なのかなど、問題形式を把握することで、読みながらどのような情報を拾うべきか判断できます。
ステップ2:本文を論理的に読む(情報整理)
設問を頭に入れたら、いよいよ本文の読解です。ここでは、筆者の論理展開を追いながら、情報を整理する読み方を実践します。
▶主語を特定する
古文は主語が頻繁に省略されます。「誰がこの行動をとったのか?」「誰がこの言葉を言ったのか?」を常に意識し、文脈や敬語の種類、会話の区切りなどから主語を推測することが最重要です。
(*本当に重要です!)
▶古文常識を意識する
古文の世界には、現代とは異なる独特の常識があります。身分制度、婚姻関係、和歌の役割、時間感覚など、古文常識を頭に入れておくことで、文章の背景が理解でき、登場人物の行動や心情がより鮮明に見えてきます。
▶敬語から人間関係を読み取る
古文は敬語が命です。
特に、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つは必ずおさえてください。
・尊敬語: 主語(行動の主体)を高める
・謙譲語: 目的語(行動の対象)を高める
・丁寧語: 話し相手を高める
どの敬語が使われているかを分析することで、誰が誰に対して話しているのか、誰が偉いのか(人間関係)が明確になります。
▶文脈の転換点に注目する
接続助詞(「〜ば」「〜ども」「〜て」など)や、話の区切りに注目してください。
特に、「しかし」のような逆接の意味を持つ語句は、話の流れが変わる合図です。
▶対比関係・因果関係を見抜く
・対比関係
「身分が低い者に対し、身分が高い者」のような対比関係を見つけると、それぞれの特徴や心情が把握しやすくなります。
・因果関係
「〜ので」「〜ため」といった原因を示す語句だけでなく、因果関係が省略されている場合も多々あります。登場人物の行動や心情の変化には、必ず何らかの原因があると考え、それを探す視点を持ちましょう。
ステップ3:解答を作成する(根拠に基づいた表現)
本文を読み終えたら、設問に戻り、解答を作成します。
▶傍線部とその前後を読む
現代文と同様、問われている傍線部だけでなく、その直前・直後の数行を丁寧に読み直しましょう。
解答のヒントや根拠は、傍線部の近くに隠されていることが非常に多いです。
▶設問の要求を正確に把握する
これは高校受験でも言われていると思いますが、一応書きます。
・「〜理由を説明せよ」なら「〜から。」で終わる。
・「〜とはどういうことか」なら「〜こと。」で終わる。
・「100字以内で説明せよ」なら字数制限を厳守する。
設問の指示は、解答作成の最も重要なルールです。
▶選択肢を吟味する(選択問題)
消去法を使う
明らかに誤っている選択肢、本文に書かれていない内容、本文の論理と異なる選択肢を消去します。
単語の意味だけで判断しない
選択肢の単語や熟語の意味が本文と合っていても、全体の文脈と異なれば誤りです。
最も適切なものを選ぶ
複数の選択肢が正しそうに見えても、設問の意図に最も合致し、本文の根拠が最も強いものを選びます。
▶記述解答の基本(記述問題)
①根拠探し
まず本文中から解答の核となる部分(キーワード、対比、因果関係、敬語など)を探し出します。
②要素の抽出
筆者の主張の「核」となる要素を、過不足なく抜き出します。
特に、省略された主語や背景となる古文常識を補いながら要素を抽出します。
③構成
抜き出した要素を、論理的な順序でつなぎ合わせます。接続語を適切に使うと、論理が明確になります。
④字数調整
記述した内容が字数制限に収まっているか確認し、削るべき部分、付け加えるべき部分を調整します。
⑤客観性の確認
自分の主観が入っていないか、本文の根拠から逸脱していないかを最終チェックします。
問題形式別の具体的なアプローチ
古文の問題は大きく分けて、内容理解問題(選択・記述)、文法・語句問題、敬語問題、文学史問題に分類できます。
内容理解問題(選択・記述)へのアプローチ
これが古文の中心となる問題形式です。
▶主語を常に特定する
「誰がこの行動をとったのか?」「誰がこの台詞を言ったのか?」と常に自問自答しながら読み進めます。登場人物の名前だけでなく、役職や身分、男女の別などもメモしながら読むと効果的です。
▶心情や状況の変化に注目する
「〜けり」(詠嘆)、「〜なむ」(願望)、「〜らむ」(推量)のような助動詞や、感情を表す言葉(例:「をかし」「あはれなり」)に注目し、登場人物の心情がどのように変化したのかを追います。
▶文脈から省略された情報を補う
古文は省略が多いため、文脈から主語、目的語、あるいは理由などを推測する力が重要です。
文法・語句問題へのアプローチ
助動詞や助詞、単語の意味などを問う知識問題です。
▶文脈から推測する
多義語や多機能な助動詞(「む」「べし」など)は、文脈によって意味が異なります。与えられた単語や助動詞だけでなく、その前後の文脈全体を読み、最も適切な意味を推測する力が重要です。
▶文法の知識を活かす
接続助詞の意味、助動詞の活用、係り結びなどの基本的な文法知識は、正確な意味を判断するための前提となります。
▶単語は多義語を重点的に
一つの意味だけでなく、複数の意味を持つ多義語(例:「をかし」「あはれなり」「やがて」など)を重点的に覚えることで、文脈判断の精度が上がります。
敬語問題へのアプローチ
敬意の対象を問う問題です。(多くの受験生が苦手だと思います)
▶尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別
どの敬語が使われているかを正確に判断することが最初のステップです。
▶動作の主体・対象・話し相手を特定する
・尊敬語は動作の主体(主語)を高めます。→ 誰が高められているか。
・謙譲語は動作の対象(目的語)を高めます。→ 誰が高められているか。
・丁寧語は話し相手を高めます。→ 誰が誰に話しているか。
登場人物の関係図を作成する
複雑な人間関係の文章では、簡単な相関図(例:A → B, C ← B)をメモしながら読むと、敬意の対象が把握しやすくなります。
文学史問題へのアプローチ
作者や作品名、成立年代などを問う問題(これも知識問題)です。
▶日ごろの学習が重要
文学史は知識問題です。重要作品の作者、成立時期、ジャンル(物語、日記、随筆など)を日頃からコツコツと暗記することが重要です。
▶時代背景との関連づけ
作品が生まれた時代背景(例:平安時代は女流文学が盛ん、鎌倉時代は戦記物語など)と関連付けて覚えると、記憶が定着しやすくなります。
今日からできる!古文読解力UPのための勉強法
ここからは古文の勉強法を解説していきます。
問題集を「解きっぱなし」にしない
▶解説を熟読する
解答解説を隅々まで読み込み、自分の思考プロセスとのズレを確認します。なぜその単語がその意味になるのか、なぜその助動詞の用法なのか、なぜこの主語が省略されているのか、論理的な根拠を理解することが大切です。
▶「なぜ間違えたか」を分析する
自分の読み間違い、主語特定や文法判断のミス、知識不足など、原因を特定し、次に活かしましょう。
精読と多読を組み合わせる
▶精読(徹底的な分析)
週に2〜3題で構いません。一文一文の文法や単語、省略された主語、敬語の対象などを徹底的に分析し、完璧に理解できるまで読み込みます。この精読が、読解力の土台を作ります。
▶多読(たくさん読む)重要!
精読とは別に、多読用の教材(例:センター試験の過去問など)を使い、数をこなすことも重要です。精読で培った分析力で、未知の文章を読む力を養いましょう。
▶古文常識を学ぶ
古文常識は単なる雑学ではありません。文章の背景を理解し、登場人物の心情を推測するための「前提知識」です。
文章を読んでいて「なぜこの人はここでこんなことをするんだろう?」と疑問に感じた時、それが古文常識を学ぶチャンスです。解説を読んで疑問を解消することで、知識が定着します。
また、古文常識に特化した参考書で、日頃から読み込みこむのも有効です。
まとめ
古文は、単なる暗記科目ではありません。単語や文法を「道具」として使いこなし、文章を論理的に読み解くことで、実力は飛躍的に向上します。
今日から、ただ読むだけでなく、設問を先に読み、論理を追いながら文章を分析し、根拠に基づいた解答を作成する「攻略法」を実践してみてください。
最初は時間がかかり、戸惑うこともあるかもしれません。
しかし、その一つ一つの積み重ねが、あなたの古文の「苦手」を「得意」に変え、志望校合格という目標への確かな道筋となるはずです。
今回は以上。
最後まで読んでくれてありがとう!
お知らせ
8月より、受験生の悩み相談や壁打ち、AI活用勉強法、英語力育成を指導・サポートする
「MIKOT塾 中高生伴走パートナー」を開始します。
詳細は近日公開!