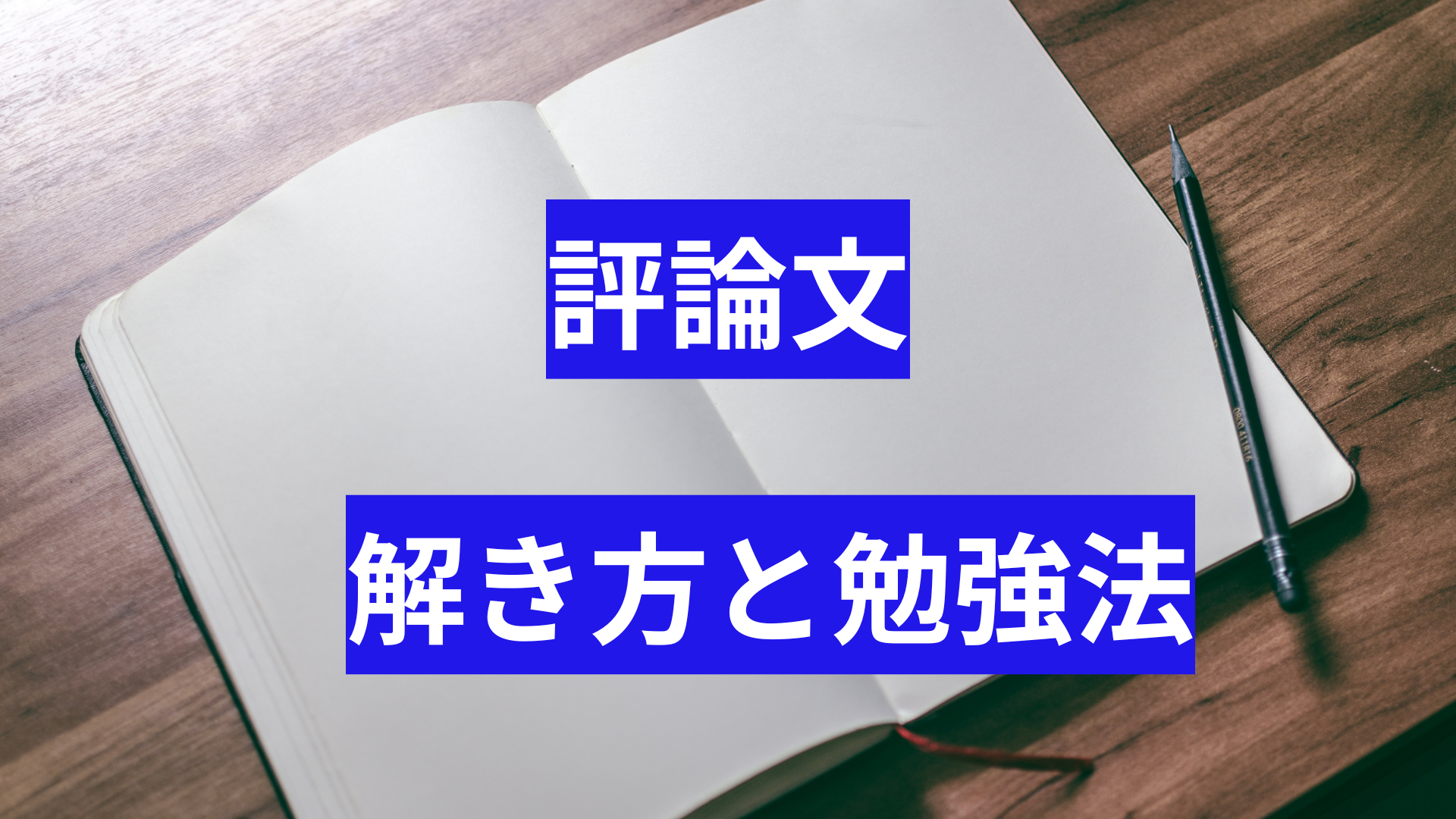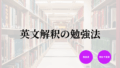今回は、大学受験における現代文(評論文)の解き方や得点UPに必要ような戦略や勉強法を解説していきます。
よく「現代文はセンスが必要」「どう勉強していいか分からない」「毎回安定して点数が取れない」と多くの高校生から大学受験で現代文に関する相談を受けます。
しかし、断言します。
現代文は「センス」や「ひらめき」で解く科目ではありません。読解の「型」を身につけ、論理的に文章を読み解く力さえあれば、誰でも安定して高得点を狙えるようになるのです。
こんな人におすすめ
・模試で現代文(評論文)の点数が安定しない人
・現代文で高得点を取りたいと考えている人
・現代文の解き方や勉強法を知りたい人
この「現代文の解き方完全攻略」記事では、現代文の苦手意識を払拭し、得点アップに直結する具体的な読解戦略と解答プロセスを徹底解説します。
*本記事では、現代文と記載されていますが、評論文と認識してください。
大学受験における現代文
現代文を攻略する上で、まず理解すべきは「大学受験の現代文とは何か」というその本質です。
現代文では、客観性が求められています。
感想文ではない!「筆者の主張」を読み取る科目
私たちが普段読書をする時、その内容は「面白い」「感動した」「それは違う」「自分はこう思う」などといった、主観的な感想や感情で受け止めがちです。
しかし、大学受験の現代文は、決して感想文を書かせる科目ではありません。問われているのは、「筆者が何を一番伝えたいのか」「筆者の論理的な展開はどうなっているのか」という、文章に明示されている客観的な情報を正確に読み取る力です。
入試の採点基準は厳格であり、個人的な解釈や感動は求められていません。
文章の中に根拠を見つけ、それを基に論理的に解答を導き出す「客観性」が、何よりも重視されるのです。この客観的な読解力が、大学で学ぶ上での基礎力として評価されます。
思考力を問うツールとしての現代文
現代文の問題は、単に文章を読みこなすだけでなく、筆者の思考プロセスを辿り、その構造を理解する「思考力」を測るツールでもあります。
さらに、この思考力は以下の4つにわけることができます。
要約力: 長い文章から要点を抜き出し、簡潔にまとめる力
分析力: 文中の対比関係、因果関係、具体例と抽象論の関係などを見抜く力
推論力: 書かれていない行間から、筆者の意図や背景を論理的に推測する力
表現力: 読み取った内容を正確かつ簡潔に表現する記述力
これらの力が、大学進学後の論文読解やレポート作成、さらには社会に出てからの情報分析能力に直結します。
現代文読解の全体像・問題を解くための3つのステップ
現代文の問題に取り組む際、闇雲に読み始めるのではなく、常に以下の3つのステップを意識することが重要です。
この3つのステップは高校受験でも同じです。
ステップ1:設問を先に読む(ゴール設定)
本文を読む前に必ず設問に目を通してください。
▶目的意識を持つ
何を問われているのかを把握することで、「どこに注目して文章を読めばよいか」という目的意識が生まれます。これにより、漫然と読むことを防ぎ、効率的な読解が可能になります。
▶キーワード・指示語の把握
設問中に含まれるキーワードや、本文中の特定箇所を指す指示語(傍線部など)を事前に確認することで、本文読解時にその箇所に意識を集中できます。
▶問題形式の確認
選択式なのか、記述式なのか、抜き出し問題なのかなど、問題形式を把握することで、読みながらどのような情報を拾うべきか判断できます。
記述問題の場合は、文字数も確認してください。
ステップ2:本文を論理的に読む(情報整理)
設問を頭に入れたら、いよいよ本文の読解です。
ここでは、筆者の論理展開を追いながら、情報を整理する読み方を実践します。
▶接続後に注目
「しかし」「だが」(逆接)、「したがって」「つまり」(順接・まとめ)、「例えば」(具体例)、「なぜなら」(理由)など、接続語は論理の転換点や関係性を示す重要なサインです。
これらを見逃さず、筆者の主張がどこで変化し、どこでまとめられているのかを把握しましょう。
▶キーワードに印をつける
繰り返し出てくる言葉、筆者が強調している言葉(「重要」「〜べきだ」「〜ではない」といった表現の近くの単語)、あるいは問題の設問に出てきたキーワードなどに線や丸といった印をつけましょう。
▶対比関係・因果関係を見抜く
・対比関係
→「AではなくB」「〜に対し〜」「以前は〜、今は〜」など、異なる概念が並べられている箇所に注目。筆者の主張は、対比の後ろに置かれることが多いです。
・因果関係
→「なぜなら」「〜によって」「結果として」「ゆえに」など、原因と結果の関係を示す表現に注目。筆者の主張の根拠となる部分です。
▶具体例と抽象論の関係を把握する
現代文の文章は、抽象的な概念を提示し、それを具体的な例で説明するという構成がよく見られます。筆者の主張は多くの場合、抽象的な概念として提示されます。
具体例はあくまで理解を助けるためのものなので、具体例に惑わされず、それが何の抽象的な概念を説明しているのかを常に意識することが大事です。
▶段落ごとの要点を把握する
各段落で筆者が何を伝えたいのかを、簡単なメモやキーワードでまとめておくと、文章全体の構造が把握しやすくなります。
ただし、共通テストなどの時間に厳しい場合は省略して構いません。
ステップ3:解答作成
本文を読み終えたら、設問に戻り、解答を作成します。
なお、本文を読みながら設問に回答していくやり方の人は、そのやり方でも構いません。
▶傍線部とその前後を読む
選択問題でも記述問題でも、問われている傍線部だけでなく、その直前・直後の数行を丁寧に読み直してください。解答のヒントや根拠は、傍線部の近くに隠されていることが非常に多いです。
▶設問の要求を正確に把握する
・設問の指示は、解答作成の最も重要なルールです
・「〜理由を説明せよ」なら「〜だから。」で終わる。
・「〜とはどういうことか」なら「〜こと。」で終わる。
・「100字以内で説明せよ」なら字数制限を厳守する。
上記は高校受験でも言われていると思いますが、一応書きました。
▶選択肢を吟味する(選択問題)
・消去法を使う
明らかに誤っている選択肢、本文に書かれていない内容、筆者の主張と異なる選択肢を消去します
・部分一致に注意
選択肢の一部が本文と一致していても、全体として筆者の主張と異なれば誤りになります。
・最も適切なものを選ぶ:
複数の選択肢が正しそうに見えても、設問の意図に最も合致し、本文の根拠が最も強いものを選びます。(当たり前の話ですが)
▶記述解答の基本(記述問題)
①根拠探し
まず本文中から解答の核となる部分(キーワード、対比、因果関係など)を探し出します。
②要素の抽出
筆者の主張の「核」となる要素を、過不足なく抜き出します。
③構成
抜き出した要素を、論理的な順序でつなぎ合わせます。接続語(「〜ため」「〜ことによって」など)を適切に使うと、論理が明確になります。
④字数調整
記述した内容が字数制限に収まっているか確認し、削るべき部分、付け加えるべき部分を調整します。余計な修飾語は削り、必要な情報は簡潔にまとめます。
⑤客観性の確認
自分の主観が入っていないか、本文の根拠から逸脱していないかを最終チェックします。
問題形式別の具体的なアプローチ
現代文の問題は大きく分けて、内容理解問題(選択・記述)、表現・語句問題、要約問題の3つに分類されます。
ここでは、それぞれ具体的なアプローチを解説します。
内容理解問題(選択・記述)へのアプローチ
これが現代文の中心となる問題形式です。
▶傍線部直前直後を徹底的に読む
傍線部がある場合、解答のヒントは8割方、その傍線部の直前直後5行以内にあります。特に、傍線部の直後に理由を問う「なぜなら」や具体例が来ている場合、その前後に答えの核があります。
▶指示語・接続語の確認
線部内に指示語(これ、それ、あれ)や接続語がある場合、それが何を指しているのか、どのような論理関係を示すのかを明確に特定することが最優先です。
▶対比構造を探す
筆者の主張は、多くの場合、対比される概念のどちらか一方を強調することで示されます。「AではなくB」「従来の〜に対し、新しい〜」のような表現を見つけたら、そこに線を引くなどして注目しましょう。
特に、筆者が否定している側ではなく、肯定している側に筆者の主張があります。
▶抽象と具体の関係を理解する
抽象的な説明の後に具体例が続く場合、筆者の主張は基本的に抽象的な説明の方にあります。
具体例は、抽象的な内容を分かりやすくするための補足なので、具体例に惑わされず、それが何の抽象概念を説明しているのかを常に意識しましょう。
記述問題では、具体例を抽象化してまとめる力が問われます。
▶本文のキーワードを優先する
特に記述問題では、自分の言葉で言い換えるよりも、本文中のキーワードや表現をそのまま用いる方が、客観性が担保され、採点者にも意図が伝わりやすくなります。
表現・語句問題へのアプローチ
漢字の書き取りや熟語の意味、比喩表現や具体例の役割を問う問題です。
▶文脈から推測する
語句の意味を問う問題では、その語句が使われている文中の前後の文脈から意味を推測する力が重要です。辞書的な意味だけでなく、文脈の中でその言葉がどのようなニュアンスで使われているかを読み取ります。
▶筆者の意図を考える
比喩表現や具体例を問う問題では、「なぜここでこの表現が使われているのか?」「筆者は何を伝えたいのか?」という筆者の意図を考えることが重要です。多くの場合、その表現が、筆者の主張や論旨をより明確にするための役割を果たしています。
▶漢字は日ごろの学習が大事
漢字問題は知識問題です。日頃から、文章中で出てきた読み書きの難しい漢字をメモし、覚える習慣をつけましょう。
要約問題へのアプローチ
文章全体の構造を理解し、筆者の最も伝えたいことを簡潔にまとめる力が問われます。
筆者の主張(結論)を特定する
まず、文章全体を通して筆者が最も強調したいこと、結論部分を見つけ出します。多くの場合、文章の冒頭(問題提起)や末尾(まとめ)にヒントがあります。
▶各段落の要点抜き出し
各段落で何が言われているのかを1文程度でまとめ、中心となるキーワードを抜き出します。
▶対比・因果・具体例を整理する
筆者の主張を支える対比関係や因果関係、具体例が説明している抽象概念を整理し、不要な具体例は省きます。
▶構成を考える
抜き出した要点やキーワードを、文章全体の論理の流れに沿って構成し直します。
▶字数制限と表現の調整
指定された字数内に収まるよう、冗長な表現を削り、簡潔で分かりやすい言葉でまとめる力を養います。本文中の表現を引用しつつ、適切に繋ぎ合わせる練習が有効です。
今日からできる!現代文読解力UPのための勉強法
現代文は一夜にして伸びるものではありませんが、正しい方法で継続すれば必ず成果が出ます。
意外かもしれませんんが、数学の考え方と似ています。
問題集を「解きっぱなし」にしない
ただ問題を解いて答え合わせをするだけでは、力がつきません。
重要なのは「なぜその答えになるのか」を徹底的に分析することです。
▶解説を熟読する
解答解説を隅々まで読み込み、自分の思考プロセスとのズレを確認します。
特に、なぜその選択肢が間違いで、なぜ正解なのか、論理的な根拠を理解することが大切です。
▶間違えた問題は「なぜ間違えたか」を分析する
自分の読み間違い、論点把握のミス、知識不足など、原因を特定し、次に活かしましょう!
▶「正解できた問題」も分析する
たとえ正解しても、感覚で解いてしまった問題は危険です。
論理的な根拠を明確に説明できるかを確認してください。
文章の「型」を意識して読む
現代文の文章には、ある程度の「型」が存在します。現代文に限らずですが…
例えば、
〇問題提起 → 理由・背景 → 具体例 → 筆者の主張 → まとめ
〇現状認識 → 従来の意見(否定) → 筆者の新しい提案(主張) → 結論
このような文章の骨格を意識しながら読むことで、筆者の論理を先回りして捉えることができます。
普段から「論理的に考える」習慣をつける
現代文の力は、日常生活の「考える力」と密接に関わっています。
▶ニュース記事やコラムを読む
新聞の社説やネットニュースのコラムなど、筆者の主張が明確な文章を積極的に読み、要点をまとめたり、筆者の意見に賛成・反対の理由を考えたりする練習をしましょう。
▶要約練習をする
読んだ文章を、誰かに説明するように「結局、この筆者は何が言いたかったんだろう?」と自問自答し、簡潔にまとめる練習をします。最初は数十字でも構いません。
▶多読
現代文の文章には様々なテーマが出題されます。
哲学、科学、社会、文化など、幅広い分野の文章に触れることで、背景知識が広がり、未知の文章にも対応しやすくなります。
まとめ
今回は、現代文(評論文)の解き方や勉強法を解説してきました。
現代文は、決してセンスやひらめきに頼る科目ではありません。正しい読解の型を学び、論理的に文章を読み解く力を日々磨けば、必ず安定して高得点が取れるようになります。
今日から、ただ読むだけでなく、設問を先に読み、論理を追いながら文章を分析し、根拠に基づいた解答を作成する「攻略法」を実践してみてください。
最初は時間がかかり、戸惑うこともあるかもしれませんが、その一つ一つの積み重ねが、あなたの現代文の「苦手」を「得意」に変え、志望校合格という目標への確かな道筋となるはずです。
この記事が少しでも役に立てれば幸いです。
今回は、以上。
最後まで読んでくれてありがとう!
お知らせ
8月より、受験生の悩み相談や壁打ち、AI活用勉強法、英語力育成を指導・サポートする
「MIKOT塾 中高生伴走パートナー」を開始します。
詳細は近日公開!