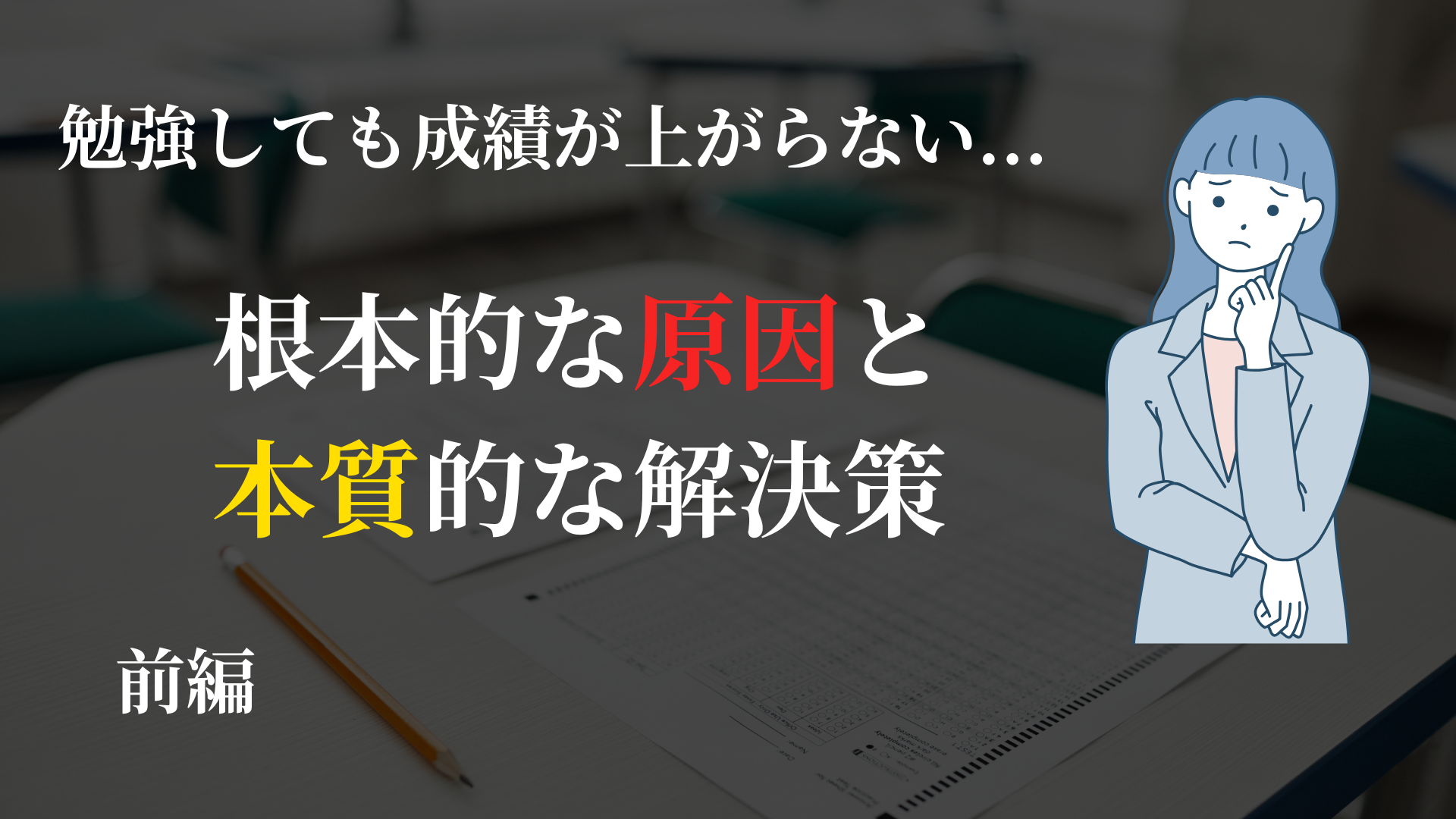今回は、勉強しているのに成績が上がらない/伸び悩んでいる中高生に向けて、その原因と本質的な解決策を書きます。
・毎日何時間も勉強しているのに、成績が上がらない/伸び悩んでいる
・なぜ、成績が上がらないのか原因がわからない
・表面的な解決法ではなく、本質的な解決策を知りたい
上記の該当する人は、この記事を読んで構いませんが、、、
今回の内容は、一般的に塾が言わない(意図的に言わない)内容になります。
人によっては納得する人と嫌悪感を感じる人がいると思います。
最初に結論から
最初に結論を書きます。
勉強しても成績が上がらない原因は、
①マインド(スタンス・姿勢)レベルが低い
②基礎固めの基準設定が曖昧
③目的と手段が混同している
④言語化レベル・読解力レベルが著しく低い
⑤勉強の作業化
⑥表面的な勉強法で勉強している
⑦インプット・準備不足
⑧生活習慣の乱れ
この8つが根本的な原因です。
控えめに言いますが、上記8つが改善されない限り、現状は改善しにくいでしょう。
この記事では①~③までの内容を扱い、残り⑤~⑧は別の記事で扱います。
マインド(スタンス・姿勢)レベルが低い
「マインド?」「そんなの勉強と関係あるの?」と思うかもしれません。
関係あります。
合格マインド
世間的には「合格マインド」と呼ばれるものです。
このマインド(スタンス・姿勢)が低いと上手くいきません。
「どうせ自分なんかが勉強しても…」
「本当に受かるのかな…」
「疲れたし、YoutubeやInstagramみよう…」
このように考えてしまうのはマインドが低い。
マインドレベルをはかる1つの指標は口癖です。
自分の経験上、「疲れた」「できない」「無理」と頻繁に言う人は成績の伸びが低いです。
逆に、「できる」「やってみます」「いけます」のような前向きになれる言葉が多い人は成績の伸びがいいです。
口癖は自分のマインドレベルをはかる指標なのです。
マインドの詳細を話すと長くなるので、今回はここまでにしますが、マインドは重要です。
成績が上がる人と上がらない人の取り組み方
成績が上がる人とそうでない人では、取り組み方が違います。
成績が上がる受験生は1問に対してそそぐ思考量と吸収量が多いです。
「なぜ、その答えになるのか?」
「なぜ、〇〇では不正解になるのか?」
「もし、問題が〇〇ならどうか?」
など1問にさく思考量と吸収量が違います。
例えば、
The cheese is made from milk.
上記からどれだけの情報が吸収できますか?
できる人は
・theは定冠詞と呼ばれ、厳密には形容詞になる。だから名詞修飾だ!
・is made fromは熟語表現で、「〜から作られる」という意味になる
・is madeは受動態の文だ
・milkは不可算名詞だからsがつかない
・fromがofに変わったら…
などなど、これだけの情報が頭に浮かびます。
たった一問かもしれませんが、この積み重ねが大事です。
「今」に全力
「今」その瞬間に対しての熱量も違います。
有難いことに、勉強に役立つ参考書や動画、まとめサイトがたくさんあります。
これらは何度も見返せるため、雑に消費しがちですが、伸びる中高生は、「今」に集中します。
その瞬間に理解して覚えようとする姿勢があります。
無意識に、その瞬間、その時間を有効活用できるのです。
成績が上がっている生徒/伸びるポテンシャルがある生徒とそうでない生徒では、マインド(スタンス・姿勢)が全く異なります。
マインドを軽視してはいけません。
大事なのでもう一度、マインド軽視してはいけません。
基礎固めの基準設定が曖昧
よく勉強法に関して検索すると「基礎固めが大事です」「基礎をしっかり勉強しましょう」と書かれています。
確かに基礎固めは大事ですが、どこまでの基礎なのか基準が曖昧です。
この基礎固めの基準が曖昧だと、
・基礎が完成していないのに、応用問題に取り組んでしまう
・いつまでも基礎ばかりやっていて応用問題に取り組めず実力がつかない
このどちらかの状態に陥ってしまいます。
英語の基礎で言えば、
・目的語になれる品詞は?
・補語になれる品詞は?
・形容詞の働きは?
・動詞の活用は?
・従属節の3種類は?
このあたりは全て基礎です。
上記が答えられない人はおそらく英文解釈が苦手です。
この基礎ができていない状態で「自分は基礎が完璧」と思い込み、応用問題に取り組んでしまう受験生が多いです。
私が8月(2025年)から開講する「MIKOT塾 中高生伴走パートナー」でも個別に基礎固めの基準設定を行います。
当然ですが、偏差値50の学校と偏差値70の学校では求められる基礎の基準も異なります。
志望校と現状の学力レベルを考慮しながら、随時、基準設定を行います。
話を戻しますが、基準固めの基準を見直してみてください。
目的と手段が混同している
目的と手段どちらが大切か?
突然ですが、目的と手段どちらが大切だと思いますか?
いきなり質問されても難しいと思うので、例を挙げながら考えてみましょう。
あなたは、今、東京にいるとし、旅行に出かけます。
次にどんな行動をとりますか?
A. 旅行先を決めてから、移動手段を考える
B. とりあえず移動手段に乗る
大半がAの旅行先を決めてから移動手段を考えると思います。
さすがに
「なんとなくでタクシーに乗りました」
「とりあえず新幹線にチケット予約しました」
という人はいないと思います。
移動手段よりも目的地を決める方が先です。
受験勉強でも手段より目的を決めることが大事です。
目的と手段の混同
多くの中高生は、目的と手段が混同しています。
参考書学習や授業を選択際によく見られます。
「とりあえず有名な参考書を買う」
「みんなが使っているから自分も使う」
「友達も受ける授業だから自分も受ける」
このように全く意図がない行動をする受験生がいます。
参考書や授業は成績アップのための手段に過ぎません。(塾や予備校の授業も)
また、参考書学習においても参考書をやりきることが目的になる人がいます。
参考書は自分の知識や理解を補う手段です。
「目的を見失った参考書選び」は、方向の定まらない航海と同じです。
大切なのは、「今の自分に何が必要か?」を考えたうえで、その目的に合った参考書や授業を選び、
計画的に活用することです。
大学受験における目的と手段
ここで大学受験を例にとって目的と手段の線引きをします。
なお、この目的と手段は視点やフェーズによって変わります。
*ビジネスのカスケードダウンの考え方に近いです。
〇進路
目的:将来、〇〇になるため(例:教師・看護師・弁護士)にその分野の知識やスキルを身につける
手段:その専門分野を学べる大学・専門学校に進学する
Point:進学はゴールではなく、夢を叶えるための手段と考える
〇大学
目的:〇〇(例:教育学・看護学・法学)など、将来につながる専門分野を深く学ぶ
手段:大学に合格するために、勉強計画を立てて学習塾や参考書を活用する
Point:合格そのものが目的ではなく、学びたいことへの「入口」だと考える
〇勉強(日々の勉強)
目的:〇〇大学に合格するための実力をつける
手段:自分に必要な勉強法(例:毎朝英単語を覚える、週1回模試を受ける、参考書学習)を実行する
Point:「目的=合格」なら、「手段=どう勉強するか」と考える
〇参考書
目的:〇〇(例:英語長文読解・数学の関数)の理解を深め、点数をとれる実力をつける
手段:参考書を読み、問題を解き、間違えたところを復習する
Point:参考書を意図もなくやるでは意味がない!「使い方」が大事です。
このように目の前の行動に対して「目的」をもってください。
| 行動(手段) | 本当の目的 |
|---|---|
| 参考書を使う | 理解を深めて、実力をつけるため |
| 勉強する | 合格するため |
| 合格する | やりたいことを学ぶため |
| 学ぶ | 将来の夢を実現するため |
コツは、「何のために?」と何度も問い直すことで、「目的」と「手段」の違いがはっきり見えてきます。
まとめ
今回は、勉強しても成績が上がらない原因を4つ説明してきました。
8月(2025年)から開講するMIKOT塾でも今回説明した
①マインド(スタンス・姿勢)レベルが低い
②基礎固めの基準設定が曖昧
③目的と手段が混同している
3つは徹底して指導します。
今、成績が伸び悩んでいる中高生は、自分の状況を振り返ってみてください。
今回は、以上。
最後まで読んでくれてありがとう!