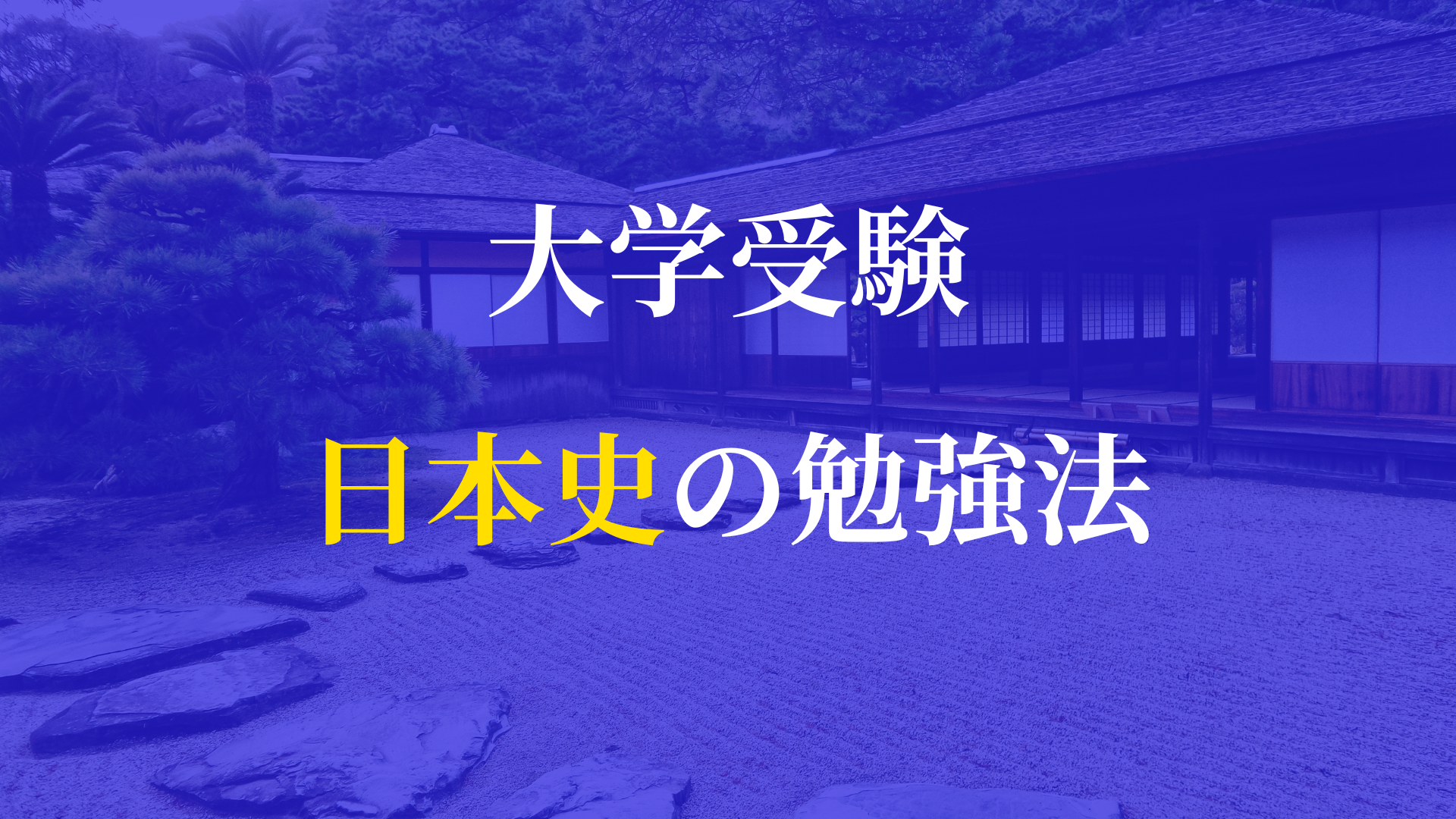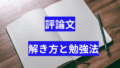今回は、大学受験における日本史の勉強法や戦略を具体的に解説していきます。
大学受験の日本史は、覚えるべき膨大な知識がありますが、単なる丸暗記では高得点は望めません。
大学入試で問われるのは、単語の知識だけでなく、「歴史の流れや背景を理解し、出来事や人物の関係性を論理的に説明する力」だからです。
こんな悩みがある人におすすめ
・年号や人名が多すぎて頭に入らない
・「流れはなんとなくわかるけど、点が伸びない
・用語は覚えているので得点できない
この「日本史の勉強法完全攻略」記事では、「暗記科目」と思われがちな日本史を、「理解と論理で解く得意科目」に変えるための具体的な学習戦略とロードマップを徹底解説します。
基礎固めから得点力アップまで、何を優先して覚え、どのように学習を進めれば良いのか、その全てを伝授します。
大学受験における日本史の本質
大学受験における日本史の本質は、「点」と「線」と「面」で捉えるです。
単なる「暗記」ではない!「歴史の流れ」を理解する科目
日本史学習で最初にぶつかる壁は、人名、年号、地名、出来事名など、覚えるべき「点」があまりにも多いことです。
しかし、これらの「点」をバラバラに覚えても、入試問題は解けません。
大学入試で問われるのは、個々の出来事が「なぜ起こったのか(原因)」「どのように進展したのか(過程)」「どのような結果をもたらしたのか(結果)」という、出来事と出来事を繋ぐ「線」としての「歴史の流れ」の理解です。
さらに言えば、個々の「出来事」(点)が「歴史の流れ」(線)の中で、どのような意味を持つのか、その時代全体、あるいは社会全体にどのような影響を与えたのかという「歴史の構造」(面)を俯瞰して理解する力が求められます。
例えば、「大化の改新」は、単に「645年に中大兄皇子が〜」と覚えるだけでなく、「律令国家形成に向けた動きの一環として、どのような背景で、何を目的として行われ、その後の社会にどう影響したか」まで理解して初めて、得点に繋がる知識となります。
因果関係・背景・影響を問う「思考力」
日本史が暗記という時代は一昔前の話です。
大学入試の日本史は、単なる知識の有無を問う問題から、より思考力を問う問題へとシフトしています。
▶因果関係
「なぜそれが起こったのか?」「その結果どうなったのか?」を論理的に説明する力
▶背景理解
出来事の裏にある社会情勢、思想、経済状況などを多角的に捉える力
▶影響分析
ある出来事が、その後の社会や政治、文化にどのような影響を与えたのかを分析する力
▶比較・対比
類似の出来事や異なる時代の制度などを比較し、共通点や相違点を明確にする力
これらを問う記述問題や論述問題、あるいは選択問題でも、深掘りした知識と論理的な思考力がなければ正解できません。
日本史学習の全体像:得点に繋がる3つのステップ

日本史の学習は、以下の3つのステップを循環させることで、効率的に実力を伸ばすことができます。
ステップ1:知識のインプット(「点」の習得)
ステップ1では、教科書や参考書、一問一答形式の資料集などを活用し、個々の「点」としての知識を正確に覚えることに注力します。
▶通史の把握
まずは時代ごとの大まかな流れを把握します。最初は細部にこだわらず、縄文時代から現代までの全体像をざっくりと理解しましょう。
古代・現代どちらからはじめても構いません。
とにかく、全体像を把握してください。
▶用語の暗記
人名、地名、出来事名、文化財名など、基本的な用語を正確に暗記します。
この時、単語だけでなく、その用語の簡単な意味や時代背景も同時に覚える意識を持つと、次のステップがスムーズになります。
▶年号の暗記
主要な出来事の年号は、必ず覚えましょう。語呂合わせを活用するのも有効ですが、ただの数字ではなく、その年号が示す「出来事」と結びつけて覚えることが重要です。
ステップ2:流れの理解と整理(「線」への接続)
インプットした「点」の知識を、「線」として繋ぎ、歴史の流れや因果関係を理解する段階です。
▶教科書の熟読
読み込みが甘い受験生が多いですが、教科書は最も正確で網羅的な参考書です。単語を覚えるためではなく、「なぜこうなったのか」という原因と結果を意識しながら、最低でも2回は熟読しましょう。
▶資料集の活用
図表や写真、地図は、文章だけでは分かりにくい内容を視覚的に理解するのに役立ちます。教科書と並行して資料集も活用し、出来事のイメージを掴みましょう。
▶横断整理
特定のテーマ(例:外交史、経済史、文化史など)に絞って、時代を横断して整理する学習です。
これにより、各時代の共通点や相違点、時代の変化における特定の要素の変遷を理解できます。
▶白紙勉強法でアウトプット
白紙のノートや紙に、教科書や参考書を見ずに、自分で時代ごとの流れや重要事項、用語の関係性を書き出す練習です。
マインドマップや箇条書き、年表形式など、自分が分かりやすい形でまとめましょう。
詳細はこちらの記事で!
ステップ3:アウトプットと演習(「面」の形成と得点化)
知識のインプットと流れの理解が進んだら、問題演習を通してアウトプットし、得点力を高める段階です。
ここでは5つ紹介します。①に関しては、好みがあるので2つ書いています。
①-1:一問一答問題集の活用
インプットの確認として最適です。ただし、単語を覚えているかだけでなく、その単語が属する文脈や意味を答えられるかを確認しましょう。
①-2:整理ノートの活用
インプットの確認として最適です。一問一答が好きじゃない人は、書き込み式の参考書でオレンジボールペンで用語を記入し、赤シートで何度も確認してください。
もしくは、「時代と流れ」のような参考書を活用するのも有効です。
②正誤問題の徹底分析
選択問題の中でも、特に「正しいものを選べ」「誤っているものを選べ」といった正誤問題は、知識の正確性と理解度を測るのに最適です。
なぜその選択肢が正解/不正解なのか、誤っている箇所はどこで、どう直せば正しいのかを説明できるようになるまで復習しましょう。
③記述・論述問題への挑戦
難易度は高いですが、最も思考力が問われる問題形式であり、日本史の本質的な理解を深めます。最初は全く書けなくても構いません。
解答例を熟読し、「なぜこの解答になるのか」「どのような要素を盛り込めば高得点になるのか」を分析することが重要です。
④過去問演習
志望校の過去問を解くことで、出題傾向、時間配分、出題形式などを把握します。解き終わった後は、必ず解説を熟読し、自分の弱点を洗い出しましょう。
「何を優先して覚えるべきか?」基礎固めの黄金律
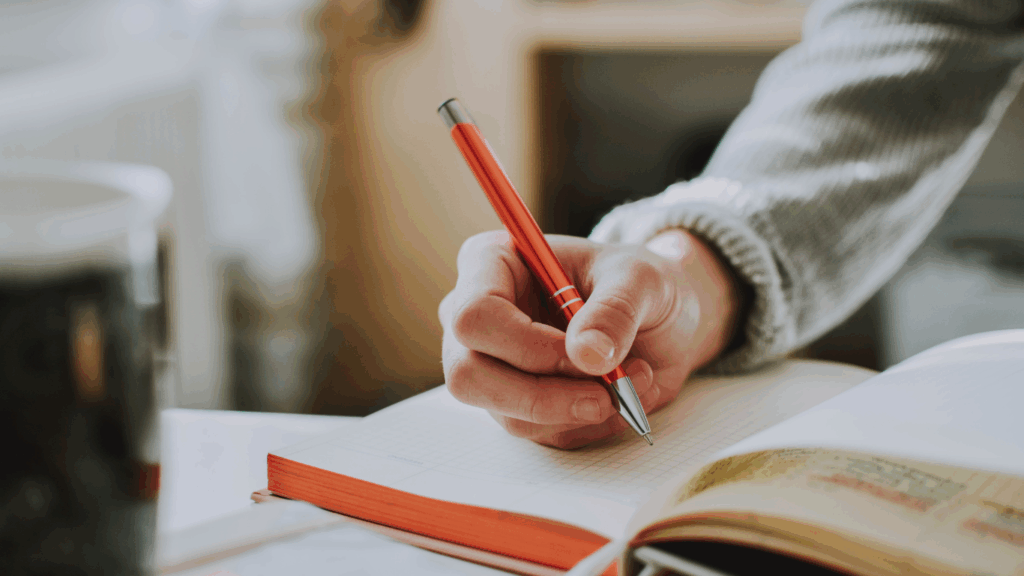
膨大な知識の中で「何を優先すべきか」を明確にすることは、効率的な学習に不可欠です。
ここでは、一例を挙げます。
最優先は重要用語と基本年号
▶重要用語
歴史の流れを理解する上で不可欠な、教科書に太字で書かれているような基本用語(人名、出来事名、制度名、作品名など)。これらが分からなければ、文章の意味を追うこともできません。
▶基本年号:「良い国作ろう鎌倉幕府(1192年)」(最近は1185年ですが…)のように、
時代区分や主要な出来事の年号は必ず覚えてください。単なる数字ではなく、その出来事が何であるかをセットで覚える。年号は「点」と「点」を繋ぐ「線」の役割を果たします。
このとき、who(誰が)、when(いつ)、where(どこで)、what(何をした)は最低限覚えてください。
次に、why(なぜ)とhow(どうやって)を確認します。
因果関係と背景
▶因果関係
「AがあったからBが起きた」というように、出来事の「原因」と「結果」を常に意識してください。
▶背景
ある出来事が起こるに至った、当時の社会情勢、経済状況、思想などを理解してください。
特に、なぜ武士が台頭したのか、なぜ鎖国が行われたのかなど、大きな転換点となる出来事の背景は深掘りポイントです。
テーマ史の学習
テーマ史の学習とは、政治史、経済史、外交史、社会史、文化史など、特定のテーマに絞って時代を縦断的に整理ことです。
大学や学部ごとに出題傾向が異なるので、志望校の出題傾向を分析したうえで取り組んでください。
ちないに、、、
文化史は、独立して出題されることが多く、覚えることが多いため、後回しにされがちですが、得点源になりやすい分野です。
時代背景と関連付けて、代表的な作品や人物、その特徴をセットで覚えましょう。絵画や建築などは資料集で実物を見ることで記憶に残りやすくなります。
日本史学習の具体的な進め方とコツ
ここから進め方とコツを紹介します。
教科書を読み込む
教科書をただの用語集として使うのはもったいないです。
大学入試の問題は教科書を基に作成されます。
教科書は、論述対策にも有効です。参考書学習が主流になりつつあり、教科書を軽視されがちですが、良書です。読み込んでください。
参考書と資料集は「相棒」
▶参考書
教科書で理解しにくい部分を補完するために使います。(あくまでも補助です)
自分に合った、解説が丁寧で分かりやすいものを選びましょう。
▶資料集
写真や図表、地図は、文字情報だけでは得られないイメージや感覚を与えてくれます。特に文化史や地理的な要素が絡む出来事の理解には不可欠です。
時代区分ごとに完成させる
一度に全時代を完璧にしようとせず、例えば「飛鳥・奈良時代」「平安時代」のように、時代区分ごとに区切って学習を進めましょう。
1.インプット
その時代の教科書・参考書を読み込み、用語や因果関係などを覚える
2.アウトプット
一問一答や時代別問題集で知識を確認し、流れと重要語句をおさえる
3.弱点克服
間違えた問題や、書けなかった用語を徹底的に復習
このサイクルを回し、完成させてください。
問題演習は「解く」より「分析」に重きを置く
▶「なぜ正解・不正解なのか?」を徹底的に分析する
特に正誤問題では、選択肢のどこがどう間違っているのかを明確に指摘できるようにしましょう。
▶解答解説を自分の言葉で説明できるようにする
他人に教えるつもりで解説を読むと、理解度が深まります。
▶間違えた問題はノートにまとめる(必要な人のみ)
間違えた問題とその正しい知識、なぜ間違えたのかの分析を記録する「弱点ノート」を作成し、定期的に見直しましょう。
ノートを作詞柄しなくても、問題集や参考書にメモをするだけでも構いません。
歴史ドラマや漫画、YouTubeを活用する
勉強の息抜きや、学習の導入として、歴史ドラマ、漫画、YouTubeの解説動画などを活用するのも有効です。これらは、歴史上の人物や出来事をよりイメージしやすくし、学習へのモチベーションを高めてくれます。
ただし、あくまで補助的なものであり、メインの学習は教科書と問題集で行うことを忘れないでください。
まとめ
今回は、日本史の勉強法や進め方について解説してきました。
日本史は決して「暗記地獄」ではありません。覚えることは多いですが、それは「歴史を理解する」ためのツールに過ぎません。
個々の知識(点)を、因果関係や背景(線)で繋ぎ、時代や社会全体(面)として俯瞰して捉える「理解」と「論理」こそが、大学入試で高得点を取るための本質的な力です。
ぜひ、日本史を「暗記科目」から理解して解く「得意科目」にしてください。
今回は、以上。
最後まで読んでくれてありがとう!